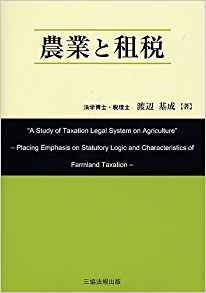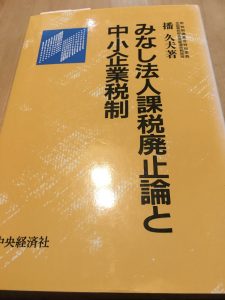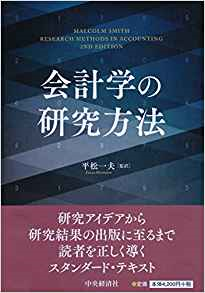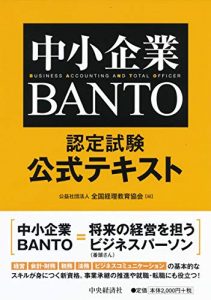記憶とは何か
人間の記憶の研究。認知的情報過程がどのようにあるのかということで、古い書籍になるが、読んでみた。なぜ、読んだかというと、記憶を通じて、どのように会計を見るのかということに対して、何か手掛かりがないかと思った次第だ。書籍は3部構成。1)日常記憶、2)作業記憶、3)再認と再生のおける付合化と検索、ということで、僕にとって、1部、2部を重要視して読んでみた。会計学に心理学を取り入れて研究したものもあるが、もう少しこの類の書籍を当たろうと思う。しっくり図式化できる、ポンチが必要だ。記録と記憶。興味深いテーマである。

何が何だかわからなくなってきた
あれやこれや論文を手直しをしている。僕も話ではだいたいよさそうだと思い、次の展開をスタートさせており、ほんと困った状況に陥っている。今回、大幅に変更、加筆とし、やりなおしてみた。正直、論文は完ぺきなものは存在せず、100人いれば100通りの答えがある。つまり、あまり構成員を増やせば増やすほど、いろんな意見が混在し、よくないと思っている。研究はやはり孤独であり、自分と指導教官の2人だけでやるべきだろうと思っている。まず困った点は、それぞれ専門領域が異なるので、自分の得意技に持ち込もうとすることだ。僕自身も意図しないことを入れる意味がわからないなど、不審が募る。これはこれで別の分野ならいいんだろうが、これはいらないだろうってのもある。まあ言っても仕方ないが・・・。そろそろエンドにしたいものだ。何が自説で何が他説なのかもわからなくなるときがある。かなりの文献をあたっているが、さらにそれに追加するとなると、自分自身にも迷いがでるものだ。解放されたい一心である、ほんと疲れ果ててしまっている。論文はやはり難しい。

広島で見たのは驚いた
今回の選挙。個人的に興味があるのは、れいわ新選組がどこまで票を獲得できるのかというところ。その一つとして、東京選挙区に現役の創価学会員が立候補したが、公明党を固める創価学会の票はどう動くのだろうかという点。権力を持つ公明党、それすがる方がいいのか、それとも宗教の信仰を是とするのか、人間の心のありようがためされている。ここのお宅、創価学会員だとうけど、比例はれいわに入れるという意思表示だと思うが、どれだけ浸透するのだろうかと思っている。政治団体であるが故、テレビなども限られているので、なかなか大衆には届きにくいが、ネットではすごいらしい。ただそれが投票に結びつくのかどうかはわからないが、どこまで行くのかなと。表題に戻すと、広島でこの風景をみたのは驚いた。少しずつ世の中が変わりつつあるのかもしれない。あと1週間、どうなるのかと思うところだ。
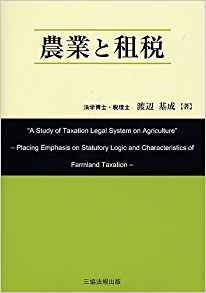
農業をめぐる税
農業をめぐる税制や税金について、誰か詳しい人いますか?と学者にも聞くことあるが、なかなかいないようである。農業会計はいるものの、やはり農学部や農学研究科などそれに類似する学会や研究科において、農業会計のコマさえないところも多い。僕も長い間、農業会計に携わっているが、現在の理解ではこうだ。①農業会計を教える人がいない、②農業会計はそこまで必要ではない、③改めてその専門家を継承する動きはあるものの、そこまでの熱意ではない。こんなところだ。①は②に起因する、③は少人数が言っているが、科目設定もされない大学をみると、そこまでの必要性を感じていないんだろうと思う。たまたま、僕もニッチなところに足を踏み入れた感はあるが、年々、農業会計研究は脆弱になってきている気がする。世の中に必要と強く思われない以上、その傾向は続くだろう。農業会計をやっていると、農業税務にも隣接分野なので、もう少し勉強をと思うが、さらにこの分野は脆弱である。もし骨太な農業経営を目指すのであれば、この分野の啓蒙は必要と思うが、大学と実務に差があるのかもしれない。一過性のブームで、学部を再編したり、新設するのではなく、もう少し専門性を高めることも必要ではないか。僕の農業会計研究もそろそろ終焉を迎えて、次のことへと思うが、少しは農業税務も見ておきたいと思うことは多々ある。それにしても、僕の人生は王道ではない。王道からそれてしまっているから、人以上に悩みが多い。農業会計にしろ、農業税務にしろ、日の目を見ることはあるんだろうか?最近、税務から見ると会計がわかるのではないかと思うことはしばしば。これはたぶん農業だけではないが・・・・。研究をする時間と心の余裕が欲しい。
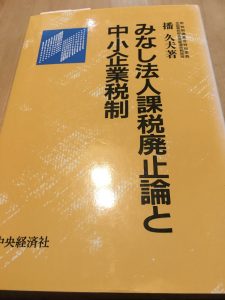
税法からのアプローチも必要かも知れぬ
平成4年まで実施されていたみなし法人課税。だいぶ昔に買っていた書籍を読んでみた。結論から言うと、立法の背景から廃止に至るまで、税制の動きがよくわかった。だいぶ昔、小規模企業税制について、まとめたことがあるが、会計においても納税の強制という観点から多大なる影響を及ぼしている。それ故に、税と会計、税務会計になるのかとも思うが、角度を変えてみるのも必要かも知れぬ。P18,19に農業法人問題が書いてある。法人化と租税回避のテーマの一部であるが、昭和32年に徳島県のミカン農家の法人化による租税回避のことが述べているが、そこには農地の問題から、課税当局が認めてなかったということもあり、訴訟事件までなっている事案のようだ。地域維持での法人化を集落営農法人でなされるが、こういう事案もあるんだなと改めてなまんだものだ。廃案を少し辿るのはいいかもしれない。それなりに立法の形成には鯨飲と結果がある。議論された内容と言葉には意味がある。ちょっと研究熱に火がつくかもしれない。

待ったなし!増税へ
先日の老後2000万円の問題とリンクすると思うが、この問題が出たのは必然であったと思っている。この問題は真実。資本主義国家であるから、基本的にすべては自己責任。だから少子化も続き、これから移民をどんどん受け入れる。そして、この国がダメだと思う人は、海外へ移住ってシナリオ。今回のテーマと離れたが、この報告書、消費税増税のための露出と僕は思っている。老後2000万円→厳しい→消費増税→痛みをみんな伴って→老後の足しにといったことを、道筋をつけたように思う。貿易の問題など確かに取り巻く環境はあるにせよ、今、上げないと、先延ばしにしても何も変わらないというロジックで、増税。今回、消費増税はすべきではないと個人的には思うが、増税はする。今回は2%上げますよって話だけではなく、軽減税率という新しい考え方をいれた消費税の法律を変えていく。そう考えると、準備を含め、やめるには遅すぎる。そう確信を得たので、仕方ないので、軽減税率も勉強しようと思っている。衆参同時選挙はあると思っていたが、なさそうだ。日本という難破船の中に、自分がいるような気がする。お金をかけず、心の満足度を高めていくといった発想かつ、倹約もして生きる。息苦しい世の中になってしまったと思う次第。軽減税率は皆さん、勉強しましょう!

老後資金2000万円時代
最近はニュースで多く取り上げてられている老後資金。報告書は事実であろうし、その状況をわめていても、変わりようがない。現実は消費税の増税や社会保険料など国民負担は増え、手取りも減る。その中で老後資金は自己責任で何とかせよということになる。政治で何とかというのはほぼ期待できない。その中で現実的に副業で資金の余剰を作るということは出てくると思う。時間的に余裕のない中であっても、何とか自由時間を経してでもそれを履行しつつ、資金を作るということはできるだろう。いわゆる時間投資だ。投資も促している。nisaにしかり、idecoにしかり。それぞれの個人がどう考えていくのか。ほんと厳しい時代だ。消費はますます減る。外食もしなくなる、飲食業も衰退する・・・・、悪のスパイラルはあちこちに。そう言いながら、自分も他人ごとではない。2000万円はなかなかたまる金額ではない。子育て支援も十分でない(子育てをすればわかる)中、あれこれ知恵を絞り、時間を投資し、何かに取り組もうと思う次第、皆さんはどうお考えであろうか。
 | 著者 : 日本経済新聞出版社 発売日 : 2018-07-12 |

文字を残す
農業会計の論文があと少しというところまできている。もう少し補強をいうことで、論文を読んでいると、引用にあった書籍の中にある論文を読みたくて、とある書籍を購入した。購入すると、非売品と書いてあり、農業会計を研究していると、必ずや当た阿部亮耳先生の退官に際し、弟子の皆さんで編集した書籍であった。内容もさることながら、阿部亮耳先生の業績や人物像なども残されており、改めて知ることができた。もう亡くなられていると聞いたことがあるが、長い月日、農業会計に向き合っていたようである。そして、業績一覧もあり、これ読んでみたいと思うような論文も散見した。書籍を残すことで後世の研究者や読者にも目に触れることがあるかもしれない。そう思うと、僕の著書もどこかでこういう機会に恵まれるとうれしい。ただ書籍は思うように売れないものだ。現実も確かに厳しいが・・・。
 | ライフデザインブックス 発売日 : 2017-12-24 |
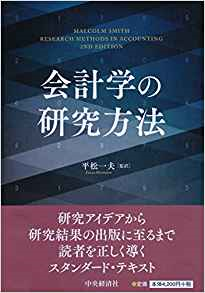
研究の手引き
学術研究をするときに、こうした手引きのような書籍があると振り返ることができる。もう少し研究手法に関して、論文もきっちり書くべきだと言われることが多い。一応は書いているのだが、どうもそれでは足りないようだ。この本は会計学の論文を書く上で、役立つことが多い。僕はヒアリングを多用する傾向があるので、研究手法の穴を埋めるように考えいくためには、そばにおいて辞書のようにつかっていたい。こうした基本書やテキストの類は、出版関係があるのだろうが、やはり高額すぎる。いつでもみんなが汎用し、使っていけるためには価格を下げてほしいものだ。会計学をやるようになって、長い時間になったが、会計学そのものを多く学んだとは言えない。こうした基本的な理論を通じて、論文を作成するといったことを、今一度、学んでみたいと思う次第だ。どの分野でもこうした書籍はあると思う。学術研究にはやはり必要なのだ。
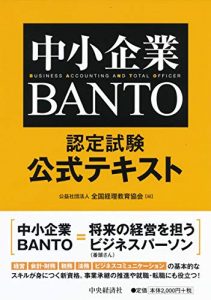
謹呈書籍のご紹介
先日、中小企業BANTO資格のテキストを謹呈いただいた。中身をみると、①分析および評価、②会計及び財務、③税法、④経営法務、⑤ビジネスコミュニケーションの5分野から構成された認定試験の学習テキストのようである。試験は来年度から実施される模様で、名前にあるように、中小企業の番頭さんの「標準」の知識を確認するといったことであろうか。資格というものは、一つの評価ではあるが、絶対的とは言えない。学習を進めるうえで、成果を積み上げるといった点ではいいと思える。世の中にあるたくさんの資格試験。この資格もどう根付いていくだろうか。基礎的な学習という点では網羅しているように思える。
 | 著者 : 中央経済社 発売日 : 2019-04-13 |