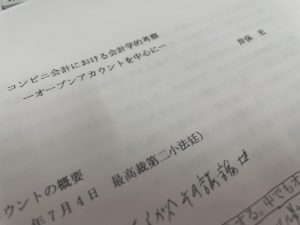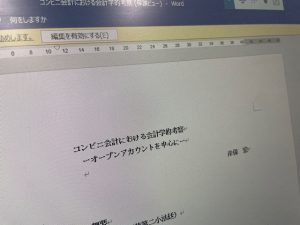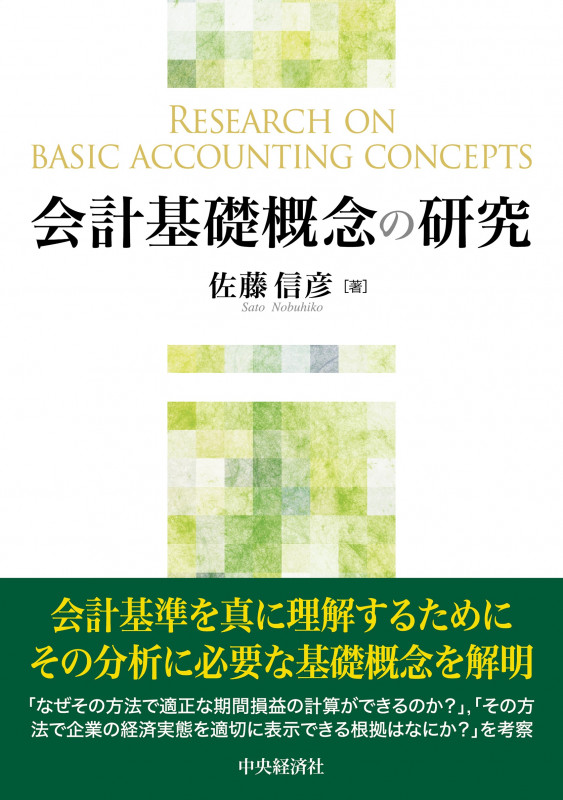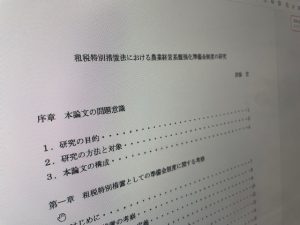利用の更新
広島大学の図書館の利用の更新時期になる。慶應義塾大学と県立広島大学とここ、広島大学を利用させていただいているが、大学の図書館は時間を忘れていることができる。広島大学は古い蔵書がある、これが国立大学の強み。最近のものは極めて少ないというのが所感である。県立広島大学はWi-Fiが使えるが、今年から利用時間が短縮した。経費節減らしいが、これは学術機関としてはマイナスである。慶應義塾大学は上京時にしかいないが、満足のいく環境。蔵書もいつも増えているし、ここは没頭してしまう。そんなこんなで使える環境があるのは幸せなこと。お金をかけず満足度の高い施設が図書館と思える。

会計の見方
中小企業の方としゃべると、会計に関して「損益計算書」を重視しているように感じる。しかし、僕から言えば「貸借対照表」をいかに見るのかと考える。それは貸借対照表は、その会社の歴史が表れており、ここを見ると、よくわかる。この意味でもっと「貸借対照表」を重視したらと思うのだが、どうしても「損益計算書」のもうけに目が向く。それはわからなくもないが、一度、「貸借対照表」に力点を置いてみてほしい。殊更、最近よく思うこと。
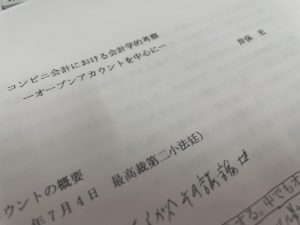
さあ!これからスタート!
6月に出す予定の論文。少し見ていただいたら赤がまあまあ入る。進歩があるのかないのかと思うところ。ペーパーコメントと電話でご指導いただいたら、なるほどと思うことが山積。この数年、コンビニ会計をテーマに積み上げていく予定。直して提出して、次へ進もう。それにしても、博士号取得は過去のもの。やはり謙虚に向き合わなければね。農業ばかりではよくないと思い、近年、興味のあるコンビニ会計の領域へ踏み込む。学術界はどのように反応するかな・・・?
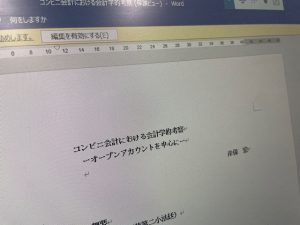
農業以外でも研究を残す!
実務でコンビニの会計を見た。少しは会計の知識があると思っていたが、見るとよくわからない。目をしかめる・・・・、まあいろいろ考えて勉強してと進めておくうちに、論文でも残していったらどうかと思い始めて、一発目を発信する。一応、脱稿し、これから推敲をしていくが、今回は「各個撃破型」。博士論文のように、大きくまとめていくのなら構成を考えて、一つ一つ仕上げるが、それはしない。自分が関心のある所から積み上げるつもり。農業もいいが、たまには違うものもね。やはり僕の研究フィールドは、社会科学にあるので。そう思いながら、チャレンジの道は続く。

懐かしい記憶とともに
熊学の指導教員の佐藤先生より謹呈本が届く。はしがきを読んでみると、入学前に体調の関係で受入れができるかどうかという話とか、まあ諸々の渦中にいたので、あれこれ話をしたり会っていたときのシーンが思い浮かぶ。いろいろあったなあ・・・。先生曰く、「焦り」と「開き直り」は僕の研究を加速させたかもしれないが、もう少し「先」にあるものをまたじっくりと酒を飲みながらでも話そうと思う。この10年くらいで研究者(もどき)から「研究者」として認められる位置までは何とかたどり着きたいと思う。会計の基礎概念に関する知識と理解が足りないという指摘は、今の研究が理論研究の軽視をどうしても感じざるを得ない。

連休明けに
5月に固定資産税と自動車税はくるのはわかっているけれど、住んでいるところは連休明けに届く。連休は皆さん、お金を使い過ぎたと思うことの方が多いのではないか。せめて連休前に届くようにしてくれた方が気持ちの上でも違うのにと思う。妻に言わせると、税金がくることはわかっているんだからお金をよけておけばいいというが、それはわかっていても心理的な問題である。毎年、思うことである。それにしても固定資産税も高くなり、何かと負担が多くなった。老後2000万円とか前は言っていた気がするが、貯蓄どころではないのか、所得から資産へというのも蜃気楼か・・・。税金も全くなしとは言わないが、重税感はあるな・・・、さすがに。

時代の流れか
企業間の決済手段として広く利用されてきた手形と小切手が、2026年度末で全て廃止される見通しだそうだ。簿記を学ぶにも手形は理解が難しい分野で、教える側になってもその気持ちはわかる。学生の顔が「??」というのがわかる。これこそ訓練の賜物である。実務でも小切手で報酬をくれる企業や倒産前に手形を切ったものをもらった経験もある(これは悪質であった経験であるが)。手形の歴史も長く、手形や小切手を知らない人がたくさん出るんだろうと思う。会計学者の端くれとしては、少し寂しいニュースかな。

1人だけの博士
熊本学園の2024年度の博士取得者は僕一人。本来は行くことのない修了式。なんだかんだでほとんど学校に行っていないので、学校の勝手もわからず終わりました。理事長の講話で熊本学園の建学の話を聞いたとき、伝統ある学校であることを知り、いい学校を終了出来たなと思い、今回、参加してよかったと思いました。一人だけが博士を呼ばれ、壇上に上がる、学位記を授与していただけるのは、この上ないことであるなと思い、2年の時間の早さを改めて感じました。その後、師匠の佐藤先生と一杯。かなり飲んでしまいました。伴奏してくださった日々をたぞりながら、熊本の地を離れます。またきますね、ありがとうございました。

ひと段落。
無事、2つ目の博士号取得!博士(商学)を授与の連絡が来ました。日本簿記学会賞を熊本学園で授与して、まさかここに自分が身を置くことになろうとは予想だにしなかった。あのときと比べて少しだけ成長して帰ってこれたと思います。まあ今回、「総代」にも選ばれて、名誉なことです。2年で博士を取ってくると自分の息子、娘に宣言して有言実行したので、子供の教育によかったと思っています。授与の余韻に浸っている場合ではない。ここでの成果は減価償却したので、次のヌーベルバーグに乗っていきたいなと思うところ。新たなるステージへ。
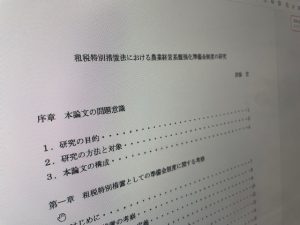
終わったぞ!
2つ目の博士論文を無事、提出しました。最後は少し疲れたな。忙しい時期というのもあるが、それ以上に校正は苦手。こまごましたことが好きではない。ざっぱな人間なので、この作業はつらいところなんだな。しかし、まあひとまず提出したので、今日は飲む。ただ次のこと、次のことをまたはじめて、新たな自分と向き合いたいと思う次第。今日だけは少し一息つかせてほしい。