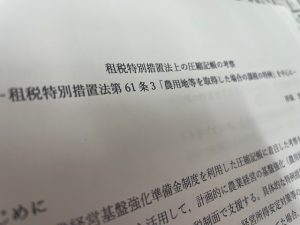
突っ走る!
10月に学会報告をしようとしている論文の初稿が上がった。いつ何時も思うが、自分の書いたもの「まあまあ」かなといつも思う。すごいいいなとは思わないのが力量なのかとも思うもの。それでも叩かれても叩かれても「書く」。この行為を続けて、なんとか人並みに追いつこうとする。これしかないと思っている。今回、熊学で残された課題とした「圧縮記帳」のお話。論文書くと、たくさん文献も読むから力つく!案ずるより産むがやすし、やるなら今しかない!そんなことで推敲の日々が続くことになる。
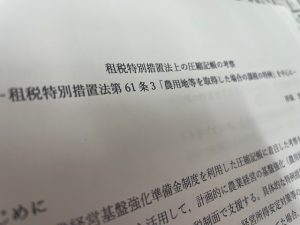
10月に学会報告をしようとしている論文の初稿が上がった。いつ何時も思うが、自分の書いたもの「まあまあ」かなといつも思う。すごいいいなとは思わないのが力量なのかとも思うもの。それでも叩かれても叩かれても「書く」。この行為を続けて、なんとか人並みに追いつこうとする。これしかないと思っている。今回、熊学で残された課題とした「圧縮記帳」のお話。論文書くと、たくさん文献も読むから力つく!案ずるより産むがやすし、やるなら今しかない!そんなことで推敲の日々が続くことになる。

廃棄トマトを利用して、釣銭トレーへ。こういうこともできるのかと感心した。食品ロスを削減し、脱プラスチックへという流れ。いい考えである。ただし商品が売れるかどうかは別の問題でですべてがオールオッケーにはならないだろうが、やはりこういう取り組みが少しずつ広がり、新しいアイデアとともに価値を作る。面白いなと思ったものだ。SDGSの流れを考えても時代には添う。JA横浜で販売しているようだが、実物をみてみたいと興味津々なのである。記事を読んで見てほしい。

半年経つと農家へ出向く。あれこれ仕事をして、雑談して・・・。今年は雨が降らない、雨期が短いこともあり、農作物の影響は大きいと予想され、収量も思うように伸びないのではないか。とすると、トランプ関税でコメの輸入は増えるのだろうかと思ったり、農業を取り巻く状況も変わってくるだろうと思える。今日は草刈の労働力の話になった。さすがに熱中症の天候、高齢化、人材不足と必要な仕事を履行できる体制が取りにくくなっている。合理的に経営も必要かもしれないが、現状も踏まえて、とかく「バランス」。これを大切にと思うのが雑感。

東広島市にある河内高校さんでお呼ばれして講義をさせていただいた。進路に関する話ということで承り、大学でやる話、専門学校である話、就職でやる話と現実論を交えて。高校ではお初だったので、どの目線で話せばいいかよくわからなかったが、ここは愛と勇気と情熱でカバー。みんな聞いてくれたな・・・。それにしても50分は短い。ほんとすぐ終わる。話し足りないので、もう少し延長したいところであったが、時間配分は慣れ。もし高校の先生なら50分で収まる講義を構成していくだろう。一度は高校で教壇になってみたかったので、夢はかなえた。やはり教壇はいいものである。

母親と買い物に行ったときにはじめて遭遇、「備蓄米」である。令和3年度産である。4年前のコメであるが、どんな味がするんだろう?興味津々であるが、こんなにはいらない。これからあっと言う間になくなるのかわからないけど、値段は手の出しやすい価格。コメは主食なのでと思うが、これは臨時対応。今後をするのか、長い目の「農業政策」を考えてしまう。

この書籍が出てから10年が経過しているが、日本の農山村の再生はうまくいっているのか。その答えはうまくいっていないように思う。農業には市場の合理主義、競争原理を導入すると、今よりもコメはなくなる。担い手がいなくなるのは自明である。合理的に考えるならば、諸外国から輸入の方法である。それだけではない、多面的機能という公益性は、経済至上主義が壊すのかとさえ思う。利益を追うことも大切であるが、人の生命を守ることを今一度、考えてはどうだろうか。10年前の書籍を読んでも現状はそうは変わっていない。さらに悪化している。まあそんなことを思いながら、古本屋で見つけた書籍を読んでいる。

フリマアプリでの米の販売を禁止という記事を見かけた。健全な取引ならいいが、転売による過度な価格競争は望ましくない。しかし、農家が直販し、販売チャネルとして活用していることを考えると、通常取引をしていた者が割を食う。現代はどうも「良心」というところの心の習慣が侵されている。法でなんでもかんでも縛るのはどうかと思うのだが、そうでもしないと歯止めが効かない。この点で言えば寂しい。それにしても、コメの取引は異常。コメはどこへ消えたのか・・・、う~んという今日この頃。

用事あって、農業現場へ。今年の田植も終わり、田園に苗が並ぶ。今年はどうなりますかね?と聞くと、まだわからんよ、そう天候不順な今でもあるし、さすがに田植したばかりではわからない。が、主食であるコメ騒動が起きている今、この「めぐみ」を頂ける喜びを再認識しなければならない。去年と比べて、コメは二倍に価格は跳ね上がっている。消費者には痛いかもしれないが、生産者は営農継続ができるような適正に土壌を作るいいチャンス。そして脳と食への啓蒙も必要。田んぼを見ながら、今の農業を考える。

随意契約の備蓄米が店舗に並び出し、長蛇の列をなしているようだ。臨時対応としては、手に取りやすい価格で流通することから評価できる。ただし、生産者のことを踏まえ、今回特例といった措置であることを周知すべきと思うが、今日の日本農業新聞で気になる記事。随意契約の備蓄米は地域差があり、関東に4割、東北、中四国は少ないようである。人口構成で多少仕方ないところはあるにせよ、関東は37パーセント、東北、中国5パーセント、四国4パーセントとかなり違うわけで、これがどこまで皆さんに行きわたるのか、そういった問題を指摘していた。根本の農業が抱える問題はあるが、今回の緊急措置を踏まえるのならば、公平に皆さんにまわるようにと思うところ。転売などはもってのほかである。
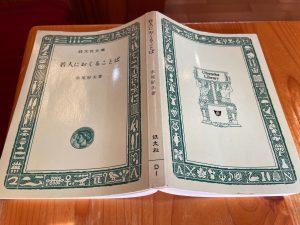
旺文社の創業者赤尾さんの著書であるが、ほんと名著である。若い頃に後悔をしてほしくないという思いも強く、書かれている。自分の若い頃の反省と今、できることを模索するためにいい人生訓ものであるが、やはりここに書かれていることは今、なお新しい。人生の勝負時はある。チャンスも多く逃してきたと思うが、後悔先に立たず。何かヒントになることをしゃべることができないだろうかとこの本を再読している。
セミナー・講演会のご依頼は
こちらから受け付けております。
