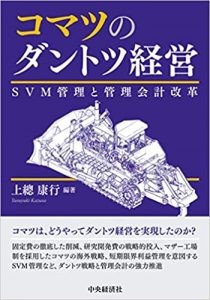税の申し子
2月16日、亡き父の71回目の誕生日である。生前、2/16 は、金正日氏の誕生日であり、確定申告のスタートの日。いろいろあるものだ。とんと性格は合わなかったが、亡くなって思うことは、親父よりもっとひどい人間がたくさんいるという事実。これは客観視できなかったところである。かといって、素晴らしい人間だったかと問われると、そうではない。しかし、これは多くを望むことが正しいということではない。僕も多くの人に会いすぎた。71歳だとまだまだバリバリの現役だぞ、普通は。忙しいから天国から手伝いに来い!所得税も結構変わったぞ。足手まといになるかもしれんが、今日という日。確認までUPしたい。

花飾り
今日の日本農業新聞の記事。花き業界が10年前からフラワーバレンタインを提唱し、気軽な花飾りの文化を作っていこうとするもの。コロナ渦中で、花き業界も需要が落ち込み、こうした新たな習慣は農家の支援にもなる。それ以上に記事にも書いてあるが、花を贈る文化、花を通じたコミュニケーションは、遠くにいる人へもいいだろう。花がある生活というのは、心を穏やかにする。イベントや冠婚葬祭も縮小(派手にできない、大勢では開催できない)と考えると、消費の落ち込みは予想できる。バレンタインに限らず、花の存在を見直す機会にもなり得るのではないか。花を選ぶ楽しさも送る側としては楽しんでみたい。
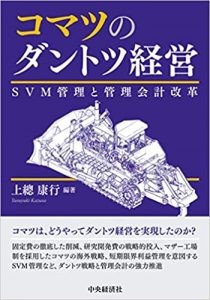
コマツの管理会計
また高尚な書籍をいただいた。学術書はやはり時間がないと読めない。確定申告が明けたら、読もうと思うが、丹念にコマツの経営、とりわけ管理会計に着目して、ヒアリング等をすすめて編纂された学術書。管理会計は、比較的実例や実務研究がさかんになっているが、やはり大規模(どこまでの規模を大規模というのか)なところを取り上げることが多い。小規模、中小企業は未分化の中にあり、研究としてはこちらを対象としたほうが個人的には関心がある。ただし、大規模は研究がしやすい一方、レッドオーシャンの研究領域なので、新たな知見を導出するのもまた大変なことではある。いずれにしても、まだ読んでいないので、それからにしよう。ありがたく感謝を込めて、この書籍をご紹介しておきたい。

自粛もそろそろ考えものだ
3か月ぶりに100名城巡りを再開させた。だいぶ感染者も減ってきたのもあるが、そもそも城はあまり密にならない。たまたまかもしれないが、我々家族しかいなかった。今回は愛媛県大洲市、大洲城である。広島から3時間半。こじんまりとしていい城だった。帰りに道後温泉に立ち寄って、坊ちゃんの湯へ。漱石の話をしながら、懐かしい気分になった。だいぶお客様も戻りつつあるようだったが、厳重な感染対策、世の中変わったものだ。自粛も大切な時期はあると思うが、今この時は帰ってこない。そのバランスを考えながら、日常を過ごすこと。少し外に出よう!

お粗末な大学
こんな記事も出ている。退学者続出 というような記事。頑張ってきた受験生は4年間あるいは2年間通う学校であり、多くの時間や労力を犠牲にして頑張ってきたと思う。コロナ・・・、確かにこの問題はあるが、決めた試験の仕組みを簡単に変更していいのか?やりようはないのか?親の立場で考えると、そんな学校に4年間の学費を払いたくない。また行かせたくない。なぜ大学だけ甘えているのか。うちの子供たち、幼稚園、小学校と普通に行っている。大学は多額のお金を徴収し、オンライン。ふざけすぎだ。要は研究がしたいために、授業はなおざりにするだけだ。インテリばかり集まってるんだから、思考せよ!親たちもそろそろ大学に抗議したほうがいいと思う。大学を少しかじる人間としてはとても情けない話である。

話題のクラブハウス
すごい勢いでクラブハウスのアプリが広がってきている。これはかなり可能性があると思う。何かやろうと思い準備を始めた。やはり音声は見直されるという僕の考えは正しかったように思う。正直、音声をどう使うのかという点でアプリをはじめ、結構調べてみた。コロナというにはマイナスでとらえがちだが、コロナだからこそこういう展開ができたというシナリオも必要である。そもそも僕の動きも変わってきているし、僕だけではなく周りもそうだろう。価値観、意識もそう。クラブハウスはとかく広がる気がしてならない。新しいことができそうだ。気になる方は調べてみるといい。数か月後にはスタンダードツールになるではないかと思っている。

○○は死にました。
タレントの石橋貴明さんが、人気番組の終焉があり、「とんねるずは死にました」と言われた記事を見た。過去に広島東洋カープの前田智徳選手がアキレス腱を断裂した際に、「前田智徳は死にました」といった発言が重なるようにフィードバックしたが、そういう心境ってのはわかる。僕も自分のことを振り返っても、「岸保宏は死にました」ということも結構ある。それはどんなときか。過去の人と会わない(直接的にも間接的にも)といけない時だ。「死んだ」のだから会う必要もない。たとえば同窓会の類い(これは誘われても一生行かない)などは無駄な時間である。過去が懐かしいとも一切思わない。「死んだ」のだから、ほっておいてほしいし、蒸し返しもしてほしくない。「死んだ」のだ。新しいスタートを切っている人間を邪魔はしない。僕もされたくない。石橋さんや前田さんとは違って、僕には輝かしい過去がない、そこは彼らと違うことだが、新しく生き直している最中に、振り返る必要にない地点に戻る必要はない。僕は過去の人の成功している姿も失敗している姿もみない。遠くで僕は言う、「ほっておいてくれてどうもありがとう!」と。

時の流れ
早いものである。1年前、博士号の最終面接の日である。前日に大学の図書館で勉強して、望んだ。農大は論文だけを出しただけの学校といえば、そうかもしれないが、1.5か月の一度くらい通っていたので、殊更思い出がある。収穫祭(学園祭)の準備時期に紹介をしていただき、春夏秋冬。数年経過したが、ようやくこぎつけた日。父の死去から事務所の再編からとかく忙しく、てんやわんや。しかもコロナが始まった時期であったし、指導教官の退官など、もう時間がないというギリギリのタイミングであった。去年のこの時期の記憶がとんとない。学術研究もほんと出来ていないし、自分に余裕がなくなっている。時間の使い方の悪さも起因していると思うが、ちょっとずつでもやっていかなければと思うものだ。論文を書かなくなると、書けなくなる。その恐怖はあるが、学術研究でも僕にとって、「残された課題」があるので、それは少なくともクリアしたい。あと学位記を目の前で授与をされてみたい。過去、すべて授与は後日しか経験がない。歳をとって、1度くらいは経験したいイベントかもしれない。コロナも1年以上、続いているのかと改めて思うことでもある。

物足りなさの一つ
この前、ある人としゃべっていたときに、亡くなった人の話になった。その人は僕をぐいぐい引っ張り、引っ掻き回されている/回しているという関係性であったが、とにかく魅力のある人だった。故人を悪く言うとかよく言うというレベルではなく、こういう人に出会うことがないからだ。とかく面白く生きさせてくれたように思う。僕も灰汁が強いほうの人間だと思うが、僕に刺激を与えてくれる人は少ないように思う。1年に1度あるかないかで、僕自身が動いて会ってみようと思う人が出てくる。その時は積極的に動いてみるが、その積極性は誰しもなく、「刺激」というスパイスがあるかどうか。ただし、会ってみようと動いても、絶えずその人が僕に刺激を与えてくるのかというのは、また別の問題である。やんちゃさも兼ね備えたり、人たらしのようなところがあったり、完璧な人ではなく、粗削りな人間のほうが僕には刺激的なような気がする。とかく物足りない空腹感はどこにあるのか。昨日思う日々雑感。

昨日の放映を経て
TSSテレビ新広島で、廣島農人の取り組みを取り上げてくださった。テレビに出るのは、ほんと久々のことである。コロナ社会になってからは発信を強めているが、さすがに地上波に出るのは戸惑いもあった。周りのみんなが出ようというのに押された感じになったが、結果的には出演したのはよかったのかしれない。これからの反響である。物事には作用と反作用があるので、それによっていい方向にすべてが出るわけではない。このブログのように、地道に継続的に積み重ねることで、「じわっと」と進む、がんぼチャンネルもそうである。地上波だと劇薬的なところもあるので、荒治療になりがちになるのは危惧する点である。ただ今回の放送を通じて、違う展開も少し見えた。「じわっと」と新たな展開をやっていこうと思っている。ああでもないこうでもないと考えて、前に進んでいきたい。