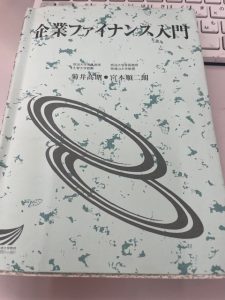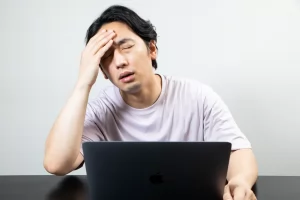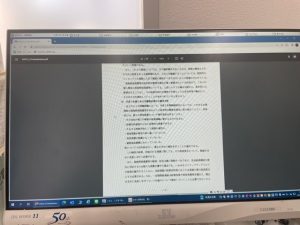大学の存在意義
少しは大学に関わっている者として、少し寂しい記事を読んだ。定員割れ、学力低下、頼みは留学生・・・。まあ現実。今、教えている学校はまさにそうかもしれない。僕自身が大学の教壇にそう魅力を感じていない。むしろ立ちたいのは高校の教壇である。何故ならば、高校が最後の教育を受ける場になるのではないか。そもそも大学に行く意味はあるのかと自問自答するからである。たくさん行った人間としては、自分の涵養を高めることにあって、自分自身の問題として受け止めてはいるが、僕の意識と周りの意識は異なるだろうし、出来れば苦労せず、大過なく過ごしたいと思う者が多いのだろう。苦労は買ってまでするものではないと思うが、それでも苦労するのだから、これも人生と思うのだが・・・。思うに大学と冠する以上は大学であってほしいと思う。それが実現しないのであれば、大学と名乗ることを辞めさせたらどうだろう?生き方はたくさんあるんだし。そう思うが、やはり悲しい記事かな。
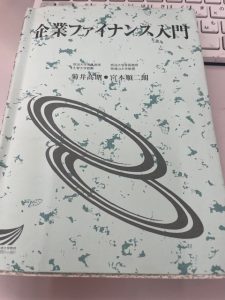
初学者の入り口
たまたま昔、勉強した本が出てきたので、思わず読み直した。放送大学のテキストである。放送大学は科目数も豊富で、初学分野にはもってこいなので、つまずいたり、入り口で勉強を始めようとするものは、放送大学のテキストのコーナーに行って探したものだ。テレビ、ラジオでも無料で講義も見たり聞いたりできる。なので、フォローもできて、本当に便利だった。MBAのときに最初、ファイナンスがわからず、購入した記憶がある。今読み直しても、たぶん入り口とは言え、深いこと書いてあるので、すべて当時分かっていたとは思えないが、何とか理解しようとはしていた。ファイナンスに関しては、他にも読んだ。わかるようになった。使いこなすというところまでは行っていないかもしれないが、蘇るように復元できる。やはりわからないより、分かった方がいい。世界も広がる。そんなこんなで約20年前のものを読むと、「あの日、あの時」が懐かしくもある。何かと必死だったのだろうと思うなあ・・・。

ブロックパズルで把握
診断士や経営コンサルタントが好んで、ブロックパズルによってお金の流れを把握させ、決算書を読む技術を伝えている。売上から変動費と固定費を引くと、利益になるが、その利益の見方である。たとえば、10の利益が残っているとすれば、そこから税金を払う。3としよう。そうすると7が残るが、いわゆる税引前の利益。そこから減価償却の繰戻しを行う。キャッシュの支出がないからであり、お金が手元に残る。仮に5を足すと、7と5を足して12になる。そこから返済があるわけだ。借入に返済は経費ではないが。税引前の利益から支出がでることになるので、仮に6とすれば、12から6を引いて、残り6。ここから個人事業であるとすれば、生活費たるものがでるわけだし、次の経営資金に回すようになるが、お金の流れ、増減、動きをたとえ、ブロックパズルでなくても、経営者はそこは把握して理解しないといけない。会計が苦手な経営者に伝える一つの術と思うが、いずれにせよ、経営者自身が勉強すべき課題で、人任せにならないということ。参考に読んで見てたらいかがだろう?

手掛かりになるかもしれない
今年は今年でしなければならないことも山積しているが、来年、一つ取り組もうと思うものがあって、ツラツラ考えた。心理学的な概念を述べる必要があるのではないかと思い、手掛かりがてら読書。この先生は習ったことがあると思う。そもそも心理学は興味のある分野ではあったが、フラッシュバックのように戻ってきた記憶。一般書で書かれてあるので、導入にはもってこいの書籍、タイトル通り、とってもわかる本である。僕の課題解決の活路になるかも。

地上波の終焉
地上波をはじめ、オールドメディアの荒廃が加速している。明らかにこちらがフェイクにニュースとなり、メディアが選ぶ「正解」へ紐づけてきた今に「NO!」が言い渡された。東京都指示選挙からネット、SNSの活用とその情報ソースの重要度、見方が変わった。確かにすべてが正しいと言わないが、「いいこと」だけではなく「悪いこと」も発信して、有権者が判断する。明らかに地上波が足を引っ張っている。CMを打つ企業も今後は地上波に出稿すれば、企業イメージが下がるということにもなるかもしれない。今回、斎藤知事が圧勝、0打ちである。オールドメディアがほんとあり方を変えないと、見放される日は来るかもしれない。メディアの「正解」は、都合の悪いことを隠すのではなく、公正公平にさらに真実を伝えることだ。そこに欠如した答え、吹き溜まりが今回の選挙になった気がする。選挙のあり方も変わる。今回の旋風をどう受け止めるのか、さあ見ものである。

珍しく面白い記事
日本農業新聞で、結婚と政治家選びについて類似性を指摘した記事を見かけた。アルマン・サラクルーというフランスの劇作家の格言で、「結婚は判断力の欠如による。離婚は忍耐力の欠如による。 再婚は記憶力の欠如による」。結婚のように、政治家を選ぶというのか、これと比較したものも面白い。はじめて出会った言葉だが、どきっとした。「結婚はしてもしなくても後悔するものである(カフカ)」だそうだ。週初めから立ち止まり、読み返したが、確かに政党がわれたり、引っ付いたりということを踏まえれば、結婚と似ている気もする。それにしても、既婚者の僕は考える。「結婚は判断力の欠如」たるもの。そう、恋は盲目?さてどうなんでしょうかと思う記事でしたとさ。

仕事はなくなるのか
とある司法書士と話をしたときに、なるほどと感心した。AIにとって代わり、士業はなくなると言う話である。こういう話はよく出る話だが、こういう意見もあると。「みんな責任をとりたくないから、人に任せるのよ」という。確かに責任問題が出る場合、逃げる人の方が多いのではないか。そう誰かのせいにする、誰かに頼る、そう考えると、仕事はあるんだよと言う。それも一理ある。士業の領域は確かに専門性もある。インターネットの発達でかなり調べてはくるものの、すべてがそうかと言えば、法改正もしかり、ついてこれているのかという判断はある。そう考えると、お金かかっても人は任せるのかなと思う。高い安いはあるけれど、この話は腑に落ちるなとお聞きした。
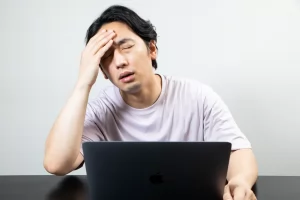
餅は餅屋か
他分野のアプローチ、そして知識の拡充という点で隣接分野にも目を通すが、真剣にその分野での活路を考えると、タイトル通り「ドツボにはまる」。やはり専門は専門な気がする、というのも、各個撃破型であれば、そこだけが理解して単元がわかればいいが、その学問の成り立ちや流れがわかっていないと、やはり本質的にはわかっていないことであり、そんなことを考えると怖くなる。自分が疑問に思っていることはすでにこの分野で解決しているかもしれないし、はたまた新しい手付かずのところかもしれない。そう考えると、まあいろいろ・・・・。そんなことを思いながら、ある論文を読んで思ったこと。
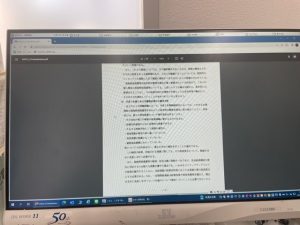
どうも「ザワザワ」
月末まで出す論文を見直している。どうも自分で書いているのに、今一歩あまりよくないのを感じる。そう思うのだから、第三者にいくと、その点は「鏡」のように跳ね返る。すなわち、「よくない」ということである。何がいけないのか。今回、出そうとしているものは、オリジナリティーはあると思う。しかし、何を伝えようとしているのかがわかりにくいかもしれない。あと文献はかなり目を通したが、その使い方が適切かどうかなど、「う~ん」というのは否めない。そんなこんなでも直していけばいいことで、出来ない自分と真摯に向き合う、この往復の中に進歩がある。ここは踏ん張りどころであろうなあと思うところだ。

盛り上がりにもかける気もするが・・・・
早急に急いでしまったが故、政権与党にはマイナスとなってしまったと感じる今回の選挙。自公で過半数が取れるのか、おそらく自民党単独では過半数を割ると予想するが、まあ最後最後までわからない。自公与党を足してもやばそうだ。どうも「ぶれている」ことが同贔屓目にみてもある。当初言ってたこととは違うよねってことが多々ある。そして党内の足の引っ張り合い。国民に向けた発信と行動に移行してほしいものだ。政治の軋みを感じる。政治とカネ、これは相当根深い。果たして週末の札はどう動くのであろうか。静かに見守りたい。