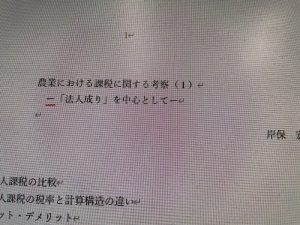久しぶりの学会報告
思えばコロナ前に学会に行ったきり、学会には参加していない。そもそも学会が好きではないので、そうは行こうとは思わない。が、今回、ちょっとやってみようかなと上京してみた。明治大学は初参上。いいところにあるね、場所も移動がしやすいいい場所。今回、論点がぼけているような気がして、報告も今一歩な気はしたが、まあこれはこれで。博士号を取得してからは非常に学術研究が楽になった。型をくずして、新しいものを作り出すチャレンジもしやすい。そんなこんなで学会。今後はいつ参上しようか、また考えましょう。

2017年の秋
農大にお世話になり、博士号をいただいたわけだが、思い起こせば、2017年秋にはじめて農大に行った。ちょうど収穫祭(学園祭)の準備時期で変わった大学だなと思ったものだ。当時は東農大と言っていたが、邪道らしく「農大」というのがいいらしい。1年間で博士を思ったが、結局2020年の春までかかってしまった。世の中、そんなに甘くない。農大は通ってみたい、学籍を持って過ごしたいような学校だった。農業に興味がなかった若いころの僕は検討さえしていなかっただろうけど・・・。

会計とは何か
会計学の分野で崇拝している友岡先生の新刊。のそりのそりと読ませていただいている。会計をできるだけ平易な言葉でかみ砕きつつ、本質に迫っている。螺旋状に会計学を1周、2周、3周とまわりながら、会計とは何かというところの到達点を見出そうとしている。この問題は僕も正直よくわからない。終わりは始まりだからだ。いつもああでもない、こうでもないと考えるが、最後は友岡先生の著書に頼る。それだけ僕には影響力を及ぼしている存在である。
 | 慶應義塾大学出版会 発売日 : 2022-10-30 |

目が文字を避ける
コロナ後遺症のせいもあろうが、とかく疲れやすい。文字を読んだり、仕事もつらい。文字に関しては老眼は進んできているのもある気がするが、それにしてもつらい。校正の作業は嫌いなものであるのもあるが、とかく後回しにしたいなと思ってしまう。さて3月末に出した論文。中国学園大学にもお世話になっているのだから、一つは足跡を残そうと思い、寄稿した。こじんまりした大学であり、肩ひじを張ることなく、楽しく教鞭をとらしてもらっている。今年も後期からお世話になるが、まあたまには論文を起こしていくことも必要なことだ。それにしても、コロナ後の体の違和感が抜けない。体のなまりであると信じたいが・・・・。
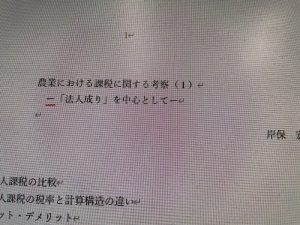
書くしかない
論文執筆も再稼働し始めた。ペンは剣より強し、やるしかない。9月末までに2本。ようやく1本目の論文執筆の初稿があがった。今回から農業に関する課税について、少しずつ整理していく予定。法人成りからスタートしていくのだが、意外とこの問題は研究がなされていないところで、灯台下暗しのようなスポットだ。あれがいいのではないか、これがいいのではないかと思いつつ、思案しながらまとめているが、この作業も決して嫌いではない。しかし、スタートするまでが時間がかかり、言い訳が多くなるのも性格かな。一歩一歩積み重ねる。これからリスタートと思い、頑張りたい。

会計と管理、会計と非会計とは?
先日、書きかけの論文が出てきて、7割くらい仕上げてあるものが出てきた。たぶん博士論文が忙しくなって、保留したのだろうが、書いたことはもちろん記憶にある。内容をみてみても、これ、ちょっと面白そうと思うので、最後まで仕上げてみようかなと思い、再スタートを切った。写真にある書籍は、博士論文にも使用したものだ。なかなか面白い考察をしているのだが、久々に引っ張り出して、再読中。副題が会計と管理、会計と非会計を考えるというワードがなければ、当時は手にしなかったかもしれない。少し時間が空いたので、書店に寄って、購入したものだ。学問も再稼働を少しずつする、エンジンをかける。楽しみながら研究をしようと今は思っている。

いい先生を亡くす
共同研究もさせていただいたし、たくさんお世話になった成川先生の訃報が届いた。62歳だそうだ。あまりにも早い。10年前に共同研究をさせていただいて以来、いろいろご指導を賜った。著書も一緒に出せて頂いているし、そのときの論文も同じくした。学会でも再会の際にはいつも気に留めてくださり、ご配慮いただいた。よく酒も飲ませていただいた。仙台、国分町で二人で飲んだ時は楽しかったし、全国いろんなところでたくさん飲んだな。学問上でも非常に読みやすい論文で、どうすればこうした論文が書けるのか指導を受けたこともある。目標だった。もう会えないと思うと寂しい限りだ。どうやっても葬儀に参列できない。その点、成川先生、お許しをいただきたい。安らかにお休みください。ありがとうございました。
 | 著者 : 中央経済社 発売日 : 2014-01-29 |

ぱっとはしないが・・・
月末までに論文を出そうと思い、ようやく書いたが、内容は今一つ。しかし、まあそれなりにというところだろうか。学者のはしくれとしても、やはり論文は書かないとと思うし、学生にレポートを課すなど,権力を持った人間からすれば、自分を律しないと教壇には立つ資格がない。だから何とか年に1本は思うところ。今年度はできれば、もう1本出したかった。どうにもこうにも忙しくて、手がつけれず、意地で1本やったが、どうもしっくりはきていない。実力不足である。それでも何とかと思うのは、自分がどうあるべきかを考えることが必要だからである。次に何とかいいものを残せるように頑張ろうと思う、それにしても悔しさの残る論文だ。

そろそろ書き上げないと・・・
確定申告の仕事が忙しくて、ほんと何も出来なかった。フルでエンジンをかけて、論文を書かないといけない。論文として残していかないといけないものもたくさんあるのも承知。いつまで経っても、タスクは減らずである。この数年、論文としては農業の税務に焦点を当てる。ただし、問題意識が違うのかなと思いつつ、また思案の連続である。苦しいことを逃げずにやるしかないんだけど、忙しいので、つい逃げたくなる。それでもやるしかない。この本はコンパクトにまとまっているので、実務家にはいいのではないかと思う。

リスタート2022
久しぶりに論文を起こしている。この2,3年は少し論文を残していこうと思っているが、僕の研究キーワードのひとつ、集落営農法人について何本かまとめようと思っている。平成13、14年ごろに積極的な集落営農の法人化を政策的に進めたが、それから20年が経過した今、集落営農法人はどうなってるのか、学術的にも実務的にも興味深い。持続的な地域保全の道はどこにあるのか、深堀しながら考えてみたいと思う。ヒアリングもたまには必要だと思うが、理論にしっかりよせて脱稿したいと思っているが・・・。