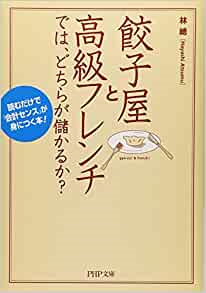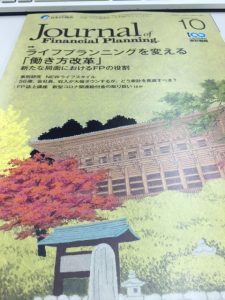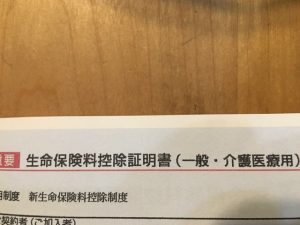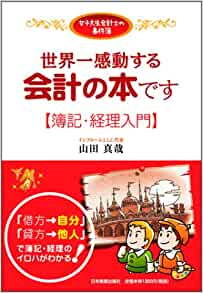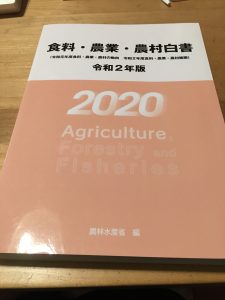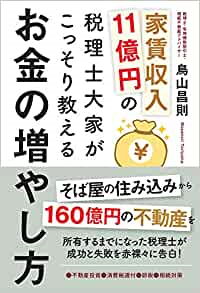慶應義塾大学へ
ずっと行けなかった東京。やはりいろいろ会いたいものだ。是非、お会いしたかった友岡先生にお会いすることができた。僕の博士論文には、マストの存在であった。正直、この先生の論文に出会わなければ、論文は完成しなかっただろう。なので、ほんと論文に出会えたことは幸福である。思い切って、塾員ということもあり、論文を送ってみた。そして、一度お会いしたい旨、お伝えしたところ、快諾してくださり、時間を割いて下さった。あれこれ誰かを介すと、あとでのトラブルもなる可能性もあるので、まあこれでいいのだろう。2時間くらい、いろんな話がdえきた。会計学の世界でも頑張らないといけない。そう思いながら三田をあとにした。いい機会であったのは間違いない。

N高校での投資体験
僕も大変注目している角川が経営するN高等学校。通信制の高校だが、みていても楽しそうだ。子供にも薦めたい学校である。部活で投資部たるものがあり、村上ファンドで有名な村上世彰氏が特別顧問した経験をつづった書籍が、画像の者である。村上財団から20万円支給し、実際の投資を経験するそうだ。非常に面白い取り組みである。本屋の平積みにすぐに手が伸びて、これから読もうと思っている。その一端は、プレジデントでも掲載されているので、読んでみるといい。お金は悪いものというかいいものとして捉えられないことが多い気がする。日本の金融教育は明らかに遅れているし、弱いところだと思う。N高等学校がこうした取り組みを取り入れたことも素晴らしいし、村上氏が投資を教えるという行為も素晴らしい。新しい取り組みが社会を変えていく。高校もそうだ。僕も通ってみたいと思うほど。学校というところにはやはりあまりいい思い出が僕にないので、何かワクワク感があるので、N高等学校は陰ながら応援している。高校生に教える投資の勉強をしてみようと思う。
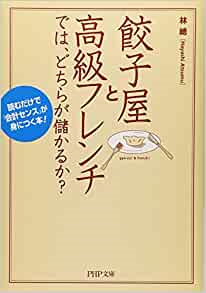
会計入門を学ぶ
以前も取り上げたことがあるが、会計をできるだけ優しくわかりやすく伝えるために、いろんな本を読み続けている。今日はこれ。餃子屋と高級フレンチのお店を例に、キャッシュフローとか管理会計とか、損益分岐点とかいろんなものを取り上げているのだが、やや高度なのかなと思う。高度というのは、一見、容易に入りやすい書籍であるが、内容が濃いいという意味だ。結構な情報は学べるのではないかと思う。それにしても、会計と会計学。学術的なものと実務的なものはアプローチは異なる。しかし、結局は使えないと意味がないので、その本丸に達成できるように考えてみようと思う次第である。じっくり考えながら、読んでみてほしい一冊。会計の本はちょっと前に発刊されたものの方が面白いと思う。

時代の予見
先日、オンラインであったが、著者の講演を聞くことができた。今は武蔵野美大の学長をされているようだ。30年前に書かれた書籍のようだが、今、ここに語られていることが現実にあるという。聞いてみて納得。読んでみて納得という感じがした。紹介までアマゾンで取り上げられている内容を、コピーすると、以下の通りである。あらゆる人びとは、デザインの能力によって今を生きている。これまで造形・美術の世界に閉じこめられていた「デザイン」は、今日情報化時代を考え、解読するためのキーワードとなった。新しい時代の価値構造の特徴は、物的価値中心指向から、知的価値中心指向への移動である。私はこの本で、〈タンジブル―インタンジブル〉という軸を想定し、時代の変容を読みとろうと試みた。この本は、グランド・デザイン構築の推進や、デザインの国際戦略活動で知られる著者が、次代を〈インタジブル・イラ(触知不能なものに価値の重心が移る時代)〉と特徴づけ検証した、俊鋭の野心作である。 著者が講演でも言っていたが、デザインの時代というか、デザインの捉え方が今問われているのは、やはり必然のような気がする。30年前ももちろん社会変化が激しかったと思うが、今、さらに加速した気がする。中古でしか手に入らないと思うが、是非、読んでいただきたい一冊である。
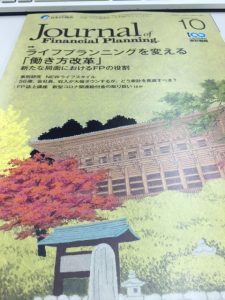
毎月の会報
すべては毎月、読めないが、FPの冊子が届く。よくまとまったもので、FPにかかわる情報がふんだんに掲載されている。FPは独占業務はないが、広がりがある仕事だと思える。お金にまつわる道先 案内をしてくれる重要な役割と思う。何か悩みがあるときに、どこに相談していいかがわからないという人が多い。すべての事柄がワンストップで解決することは、なかなか難しい。ただこういう広い範囲で継続的に学ぶ体制がFPにはしっかりできており、自己研鑽にも役立つので、その道先案内という点では十分な素養があるように思う。どこでどうビジネスにつながるかはわからないが、人にはそれぞれ役割がある。それを全うしつつ、生きる道を模索したいと思う。FP系の雑誌はおすすめである。その時々のトレンドがうまく整理されている。
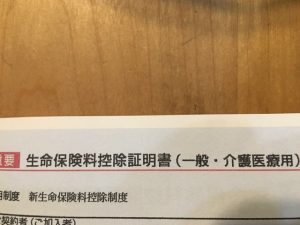
今年もこういう時期か
生命保険料控除のはがきが自宅に届き始めた。そう考えると、今年も終わりが近くなっているわけで、また歳も1つ重ねるわけだ。生命保険料控除も、介護と年金にもわかれ、僕が最初に年末調整をしていたころとは変わった。マイナンバーを必須としたりと、時代の変容を感じる。年末調整も本来はやめて、アメリカのように自分で申告をしたほうがいいと思う。納税意識は必ず高まるし、会社負担も減る。申告会場は殺到するかもしれないが、これからのデジタル化。少し考えてはどうだろう?税理士いらずの世の中になるかもしれないが、まあこれも時代の流れだと思うのだが・・・。気づけば、10月。今年も終わりの音が聞こえ始めた。

頭がついていかない
コロナになってから補助金・給付金など制度がたくさん作られ、なかなか頭がついていかない。既存の補助金なども並行に新設されている。国・県・市・民間、多種多様、用途もいろいろ。これだけあると、ほんと大変である。4月くらいから自社も含めて、たくさん書いた。農林水産省、経済産業省、厚生労働省・・・、自治体など、だいぶ知識もついた。補助金ビジネスをどんどんやる人もいるが、それはあまり好きではなく、むしろ経営する自社に活用できる補助金を使って、ビジネスを組み立てていくことに興味がある。情報をどう収集し、活用するのか、使えるものは使うべきであろう。
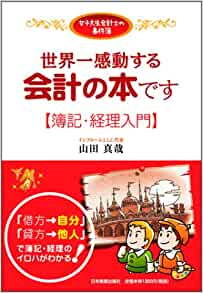
分かりやすく伝える・学びやすい
15年前くらいに会計ブームというのがあって、会計の本が売れないと言われたのを打破してきた時代。その時の本であるが、このころの本を大量に購入して、少しずつインストールしている。いろいろあるが、今日のこの本。山田真哉先生、さおだけの本で有名になったと思うが、非常にわかりやすい。かなり使えるなと思っている。会計はやはり難しい。だから会計を難しいと知りつつ、できるだけ教える方はかみ砕いて伝える。教わる方は、やはり受け入れやすい。図にする?言葉にする?いろいろ。会計ブームの時は、本もたくさん出ているが、学びが大きい。わかっている人も読んでみるといいと思う。
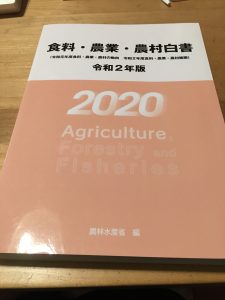
年々遅くなっている気がするが…
毎年、農業白書を購入する。さすがに全てを読むことはないが、辞書として活用する。早速、廣島農人のラジオで資料がわりで使わさせていただいた。白書と放送大学の教科書はかなり役に立つ。学術研究にもかなり役立つから、是非、自分の関心がある分野は目にするといい。買うのが抵抗ある人は図書館の利用である。まあ一度、手にとって欲しい代物である。
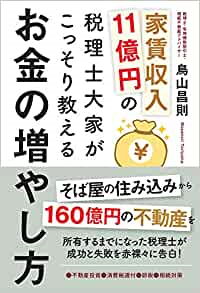
不動産賃貸業も事業です
まだ不動産価格は高い相場観はあるが、少しずつ値も崩れ始めている気がする。何分、売り物件がまだまだ少ないが、これから不動産を手放していく傾向はあるように思う。僕自身も不動産賃貸もしているが、この手の本は、ちょこちょこ読むようにしている。比較的多い投資をするにもかかわらず、不勉強な人は多い。僕も同じようなことが書かれていても、復習のつもりで読む。勉強する。不動産はインフレ時に強いなどメリットもあるが、当然にデメリットもある。しかし、何もやらなければ何もない。当然の帰結であるが、不動産を投資をし、お金の勉強をすることも大切な営みではないかと思う。税金もそうだし、投資効率もそうだし、登記なんかもそうだし・・・。一つの出来事で学ぶことは多い。この書籍は税理士さんが書かれた本であるが、節税なども書かれている。この類は多い部類の話であるが、いろいろ知識をインストールするといい。これから格安で不動産を得られることも出てくるように思う。有事に備えることだ。