地域の事例から学ぶ
長い休みの時は、同じ人の著書を何冊も読む。今回は金丸弘美さん。ちなみに男性。6次産業や地方創生など地域活性化の支援をされているようだ。地域の事例を取り上げながら、十分に自身も活用できそうなこと、あるいは導入してみようと思うもの、そして応用できるものと、勉強をさせてもらった。6次産業にはやや否定的な立ち位置でみている。農商工連携に力をいれるべきだと思っている。今年は農家の支援を頼まれているところがあるので、半分、プレイヤ-で取り組んでみようと思う。
長い休みの時は、同じ人の著書を何冊も読む。今回は金丸弘美さん。ちなみに男性。6次産業や地方創生など地域活性化の支援をされているようだ。地域の事例を取り上げながら、十分に自身も活用できそうなこと、あるいは導入してみようと思うもの、そして応用できるものと、勉強をさせてもらった。6次産業にはやや否定的な立ち位置でみている。農商工連携に力をいれるべきだと思っている。今年は農家の支援を頼まれているところがあるので、半分、プレイヤ-で取り組んでみようと思う。
先日、支援している農家に訪問した時のお話である。株主として企業参入している人と農家のせめぎあい。前者は利益重視であり、損益分岐点を探ろうとしており、その数値化により小さいものが少しずつ大きく展開していけば、大きくなる事業計画を策定したい。後者は売上重視であり、レバレッジをかけて、投資する。拡大すれば、使えるお金も大きくなり、経営展開が広がっていくという考え。どちらも同じゴールは求めているが、その道程がかなり違う。農業経営の管理をどのように数値化し、見えるような会計システムに作り上げ、活用するかは非常に重要なファクタ-である。僕はスモ-ルファ-マ-が増えれば、大きくなるという考えと、莫大な資本を投下できる企業でない限り、掌の中で商売はすべきという考えである。少しの無理なら挽回できるが、それが挽回できなくなる可能性がある。農業の場合、労働力も高齢化から時間単位で測定すると、やはり効率は悪いはずである。また天候に左右される業種を考えると、合理的に進みにくい。変動を加味しないといけないわけである。今回の議論は農業に留まらない、中小企業の問題としても立脚する。大企業もそうだろう。会計で言うと、一つ「変動損益計算書」は使ってもらいたいツール。管理会計はあくまで使う経営者の意思決定だから、強制するものはない。たくさんあるけど、この計算書はもっと使われていい管理表であると思っている。
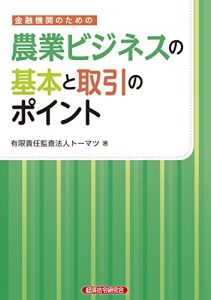
農業を入り口にいろいろ考えてきて、行動もした。農業支援からはじまって、加工・飲食への広がりの中で、学術研究においても拡張せざるえなくなってきたというのがある。農業は生産の部分であるが、加工・飲食販売になると、やはり違う領域として、理論立てた計画が必要になる。あれこれ思いながら、農業を核とするならば、「食」、「医療」、「福祉」、「畜産」、「雇用」・・・・、様々な分野で連携や相互補完できる。農業ビジネスのあり方、そしてその考え方にもう一度、捉えなおして構築していくことが必要と考えている。ひとまず飲食業の連携の中で、僕なりの整理をしていきたいと最近思っている。
僕自身がクラウドファンディングの推進のお手伝いをしているが、これも使い方ひとつで全く効果は異なると思っている。資金調達としての位置づけで考えれば、銀行借り入れよりはるかに高い金利であり、選ぶべき手段ではないと判断されよう。しかし、商品のプロモ-ション費用として位置づけると、①顧客の獲得、②利益の確保、③資金調達といった形で、並行したアクションが起こせることになる。銀行借り入れだとその調達資金を運転や設備といった資金にまわるのみになる。しかし、クラウドファンディングの利用によって、投資家がファンに転嫁し、顧客になっていくシナリオは、いろんな分野で役立つと考えている。農業に鑑みても、思いや熱意をどう伝えていくか、どうPRしていくのかを、こうした方法によって、掘り起こし地域のスーパ-スタ-を作っていくことも可能だと思っている。現在、内閣府も投資型クラウドファンディングを、「ふるさと投資」と位置づけ、活発な市場を作るプラットフォ-ムを構築しようとしている。うまく使えるかどうかでまた大きく変わってくるのだ。農業の挑戦の選択肢として、考えてみてはいかがであろうか?6次産業化の認定よりはるかにハードルは低い。
2011年に農業簿記にかかわってから、自分の農業会計研究も「簿記」というものに着目して、章の一部になってきたような気がする。そもそも僕のくぐりとして、修士の際にまとめた農業会計の課題を学会で報告してみようということだったが、たまたま縁あって、農業簿記の部会にまで携わることになった。これも縁で学会賞まで共同であるが、いただき、画像の書籍もまで発刊。財務会計の世界にもヒアリングを重視した点が良かったように思う。そのときから日本簿記学会にも参加するようになって、今年の5月に久しぶりに報告したものを、今回、投稿する。簿記の領域が特に関心がつよいわけではないが、今回の整理したものは、簿記の領域で語るべきだろうと思っている。簿記にさかのぼることも必要なことである。査読が通るのか、わからないが、チャレンジあるのみ。学者はあらさがしが好きな人たちなので、またあれやこれやと出てくるんだろう。僕がそこにチュ-ニングすればいいのだが、僕にもプライドがあるので、譲れないところは譲らない。でも論文には意義がある。
これまでの農業にかかわった経験や視点、考えをまとめるべく、書籍を出すことにした。幸い、縁があって出版社も応援してくれている。しかし、なかなか思うように時間もとれないのもあるが、執筆が進まない。これはやる気の問題もある。どうしても日常に加え、論文の執筆もあるし、あれやこれやでほんと思うようにいかない。時たま、出版社から催促の連絡があるが、ほんと申し訳ないが、書けていないの事実だ。今回、書籍にまとめることは意義があると思っている。僕のかかわった物語を通じて、メッセ-ジを残すことで、ひょっとしたらまた新しい農業を応援する人が出てくるのではないかと思っている。僕も書籍から元気をもらうことも多い。内容がそうなればこの上ないのだが・・・。何をするにしても、まとまった時間が欲しい。漸くまとまってとれたかなと思った時間も、家族中の風邪で、何かをするどころではなかった。いずれにしても、自分がやるかやらないかという選択である。どうせやるなら楽しくやりたい。
サスティナブルな農業経営を行うためにも、「儲ける」という利益至上主義を第一義的に念頭に置かず、地域や自然を一体化しつつ、農業に向き合うことが大切になる。こうした視点の中で、説明を加えられている一冊。特に企業の農業参入には役立つ。先進事例から事業計画も含め、農業+αの部分を学べる。高収益な農業ビジネスを実現するために、どう付加価値をつけていくのか、難しい課題でもあるが、ビジネスはここを超えないといけない。
農業を支援する会社、株式会社マスタ-ド・シード22の起ち上げの時に、ケーブルテレビに取り上げていただいたDVDが出てきた。今では規格外野菜を使ったアイスクリ-ムの展開が主だったが、最初は「米」をテーマにしていた。米も支援を行っていなわけではないが、米のブランド化は非常に難しい。かつては、米と環境、環境と言っても「水」に着目し、良質な軟水で育てたという視点でPRを試みたりと、あれこれ考えていた。地域ブランドを創造するという理念を掲げ、はじめた会社ももう6年経過している。なかなか思うようなところまでにはないが、人的ネットワ-クからはとてつもないものを得ているような気がする。紆余曲折しながら、時間は経過しているが、なお一層、農業支援を行える展開をし、活性化していきたいと思っている。
6次産業化は、生産、加工、販売を一体的な取り組みを行うことを目的としているが、その取り組みは否定はしないが、本当にこれでいいのだろうかと懐疑的に思っている。つまり、生産者側から言うと、少々の規格外でも食べるという観点から気にならない者のの、売る立場からすると、これでは商品にならないということになる。形状や規格の面が整わなければいけないわけである。プロという専門性を分業すれば、その立場で厳格な基準をもとに仕事をしていく。妥協がそこにないわけだ。じゃあ規格外といわれるものやその規格にあわないものはどうするのか、これは別の市場があるわけで、その生産物を売るプロは売るプロとして仕事をする。作るプロは作るプロで絶品の生産物を作ることに従事したほうがよりよいのではなかろうか?どの世界でもそうだが、あれもこれも取り込み過ぎた感がある。分業という視点で改めて、考えてみたらどうだろうかと、最近思うことである。
投稿予定の論文に有益と思い、購入した書籍。前々からこの書籍は知っていたが、今回、財務管理という視点がどうしても必要なときに、他の方が引用文献の使用されていることから、改めて知った経緯である。農業経営の入門的に整理されており、たぶん教科書で使用されている学校もあるような本であった。農業の財務管理はなかなか見当たらず、先行的なものを手掛かりにする際にどうしても必要である。今回、再発見できた視点もあり、学術的導入では非常に読みやすくわかりやすいと思える。理論と実践を融合させていくのは、農業経営のみならず、必要な事柄だ。理論を軽視してはいけない。
セミナー・講演会のご依頼は
こちらから受け付けております。
