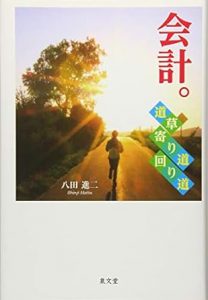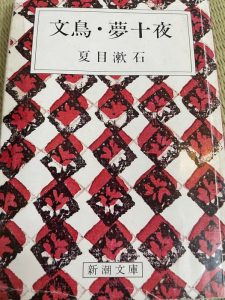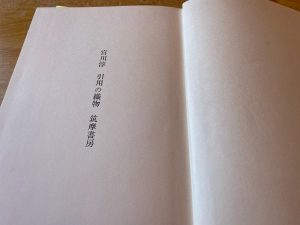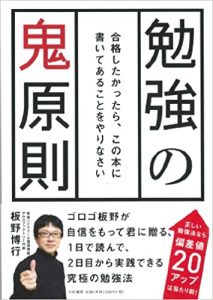久し振りに一般書
東京15区の選挙にでている福永弁護士の著書。気になって著書があったので、読んで見た。楽しく読めた。たとえば、P126。「ゆっくり考えて1つを試すより、スピーディーに3つ試す」という件。決め打ちをしないで、動きながら検証するとか、肩書に縛られないとか(P216)、キャリアの連続性を考える必要がない(P219)など、同じようなことを考えているなと思うこともたくさんあった。なぜ選挙に出たのか、わからないが、それぞれの生き方、考え方があるけど、新しいことにチャレンジをし続けたい人なのかなと書籍からも感じることであった。一読をおすすめする。
 | クロスメディア・パブリッシング(インプレス) 発売日 : 2019-07-12 |
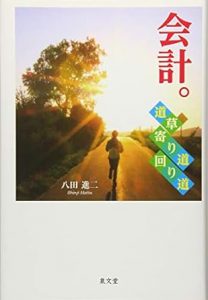
僕からしたら斬新
会計学を大学で教えている身からすれば、「会計」とあると反応する。パブロフの犬ではないが、ブックオフによった際に見つけた本である。基本的には買う前は目次程度でも中身を見て買うが、この本は価格も見なければ、中身も見ずに購入した。何故か、「会計。」というタイトルはストレートで斬新、とてもいい。副題はあるが、それは付随したもので何か期待されるものであった。もう一つは、研究者をやっていると八田先生のお名前は聞いたことはあるもので、素直に学んでみようと。そんな話である。中身である。会計大学院のことを含め、会計プロフェッションの育成について真摯に意見を述べられている。会計軽視にある状況に看過できない、あるいは危機感を抱いていることが十分に伝わる内容であった。会計プロフェッションの育成までいかなくても、会計軽視というか会計の重要性といったところを教えられれば(学生に伝われば)と思うが、果たしてどうだろうか。コラムでいいので何か、こういうお考えをさらに公開して読みたいと思うものだった。

ミドルな微妙な年齢
最近、年齢がタイトルにある書籍や雑誌は気になる。40台で言えば、もう少しで終わり、50歳も近いので、40歳、50歳と書かれているものである。40歳をユングは人生の正午といい、今の僕は午後にあるが、真意はこの通りである。「午前の太陽は昇る勢いはすさまじいが、その勢いゆえに背後においやられたもの、影に隠れてしまったものがたくさんある。それらを統合していくのが40歳以降の課題」としているという意味で、これからの人生の景色や風景は違うのであるということ。この手の書籍はこれからも手に取りそうだ。人生、充実或る過ごし方をしたいとかねがね思っているので、何らかのヒントになるような気もしている。もう少しセルフィングすることになろう。

子どもに読ませようと
新5000円札に選ばれたこともあったし、自分自身、津田梅子という人のことを良く知らないのもあって、この書籍を買ってみた。子供に読ませたいとおもって、岩波ジュニア新書を選んでいるが、ちょこちょこ津田梅子に関して文庫などもあるようだ。津田塾大学のことは知っていたが、この時代の女性の活躍の場を形成することの難しさや格闘を知る。新5000円札でもなければ、向き合うことはなかったかもしれない。特に娘には読んでほしいが、まだ低学年では難しいだろうから、長男にまずは思うところだ。
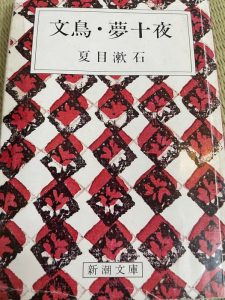
楽読、楽して読むのではなく、楽しく読む。
漱石再読。文鳥編。それにしてもなかなか進まないが、期限あるものではないので、ゆっくりと。文鳥。早稲田に引っ越してきた漱石が鈴木三重吉にすすめられて、文鳥を買い、2日ほどかまわなくて死んだという話で、昔知っていた女の回想を織り交ぜて、美しいものの死を描いている作品。あまり読むことのない小説ではないかと思う。分量もそうはない。小品。女が漱石に潜む夢としてあり、ここに収集されている夢十夜にある意識ともつながってくる。夢十夜はまた綴るとして、ようやく前期三部作へ読み進めようと思う次第。

大学受験の参考書から
古本屋で見つけた書籍。センター倫理、今は共通テストと名前も変わっているが、その参考書である。センター試験の過去問題と解説、人物をピックアップしているが、なかなか面白い。正解するものもあるが、不正解もありながら、楽しんで読み解きをしている。受験や試験となると、成果が伴わないと無意味ともいえるが、教養を高めるという点で読むと面白さが十分にある。文庫本にして、一般人にも手に取りやすいようにすればいいのではないかと思うような書籍。なかなかいいな!

覚悟をすること
読書の時間もあるようでない。だから本だけは購入していてもいつ読めるのか、そのままなのか。なかなか読めなかった本であるが、面白い。今、立憲民主党に行ったので、出版時期と見方は違うところがあるが、無所属で小選挙区で勝ち続けた中村喜四郎先生のお話であるが、心が強いなと感心する。名前も父親と同じ名前に改名し、徹底した姿勢、選挙、地域とのかかわりなど、いろんなことを学ぶ契機になる。最近は、政治家と接点をあまり持つことを望んでいないので、近づきもしないから状況はわからないが、ああこういうこともあるんだなと思うことはしばしば。政治家にも覚悟がここまである人は少ないと思う。

エッセンスを学ぶ
こういった会計の初歩を学ぶ本はどうしても気になる。大学で教えるようになって、何が基本で、どこまでは学んで血肉化してほしいのか、とかく考える。今回、見つけたのはこの本。簿記と会計の違いとか、流動資産と固定資産の違いとか・・・、比べて理解を促すように構成されている。板書中心の講義をしているから、こうしたエッセンスを取り込みながら、初級者にいただけるように、あれこれ工夫をするものである。これから読み進めるが、面白そうなので、一度読んでみたらどうだろうと思う会計の本。
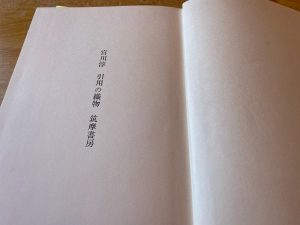
ふと思い出した言葉
引用の織物。ロラン・バルトを思い出したわけだ。テクストとは、無数にある文化の中心からやって来た引用の織物であるという。模倣と独創。ほんとに独自性は自分にあるのだろうか。引用の織物と検索したら、宮川淳さんの本が出てきた。僕が生まれる1年前に出版している。p117。「なぜ引用なのか。引用について考えること、それは読むことについて考えはじめることだ。読むとはアルケー(原理とか根拠という意味)、一なる全体、《本》へと送りとどけることではない。それは逆に還元不可能な複数性、くりかえしと差異について考えることでだろう」という一節があるが、くりかえしと差異。深く考える。続いて、他社への存在を記しているが、殊更、何か自分が自分であるような、ないようなそんな感覚を感じるときがある。楽しく読ませてもらった。
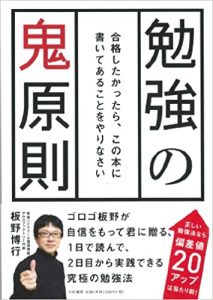
やる気と持続と・・・
大学受験用に書かれている勉強法の本であるが、たまにこうした勉強法の書籍を読むようにしている。概ね同じようなことが書いてあるが、たまにこれ使うと効率がいいのではないかと思うこともある。限られた時間と先にある試験、あるいは資格などを突破するにはという点も当然だが、こうすれば理解が深まるかなとか、まあいろいろ思うこともある。何点か参考にしてみようと思うこともあった。たまに自己啓発や勉強法の本は読むといいと思う。