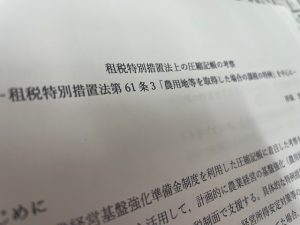
突っ走る!
10月に学会報告をしようとしている論文の初稿が上がった。いつ何時も思うが、自分の書いたもの「まあまあ」かなといつも思う。すごいいいなとは思わないのが力量なのかとも思うもの。それでも叩かれても叩かれても「書く」。この行為を続けて、なんとか人並みに追いつこうとする。これしかないと思っている。今回、熊学で残された課題とした「圧縮記帳」のお話。論文書くと、たくさん文献も読むから力つく!案ずるより産むがやすし、やるなら今しかない!そんなことで推敲の日々が続くことになる。
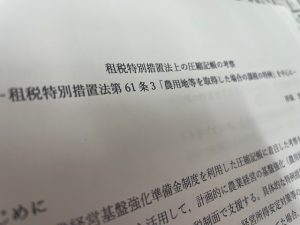
10月に学会報告をしようとしている論文の初稿が上がった。いつ何時も思うが、自分の書いたもの「まあまあ」かなといつも思う。すごいいいなとは思わないのが力量なのかとも思うもの。それでも叩かれても叩かれても「書く」。この行為を続けて、なんとか人並みに追いつこうとする。これしかないと思っている。今回、熊学で残された課題とした「圧縮記帳」のお話。論文書くと、たくさん文献も読むから力つく!案ずるより産むがやすし、やるなら今しかない!そんなことで推敲の日々が続くことになる。

朽木糞牆(きゅうぼくふんちょう)と読むが、論語にあるようで、僕は知らなかった。腐った木とぼろぼろの壁という意味から、どうにも手のつけようのないさまをいう。とくに、もともと意欲や素質のない者は、手の施しようがないということをたとえていうそうであるが、今の政治と絡めた論評をして記事を読んだ。「国難」の今をみて、国家という建物はボロボロ。柱も壁も朽ちかけている。大黒柱の経済は停滞し、人口減は止まらず、離農や離村も後を絶たない。食料も防衛の安全保障も危機にさらされ、成長が見込めない比喩の中に何を見よう。古典には今に通じる「知」がある。自分の課した課題が終えれば、もう少し学びを深めていきたいと思うのだが、うまく事が進んでいないのも現状である。
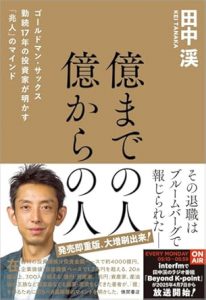
平積みになっている書籍を読む機会は少ない。専門書を読むことが多いのもあるが、本屋では流行を眺める程度。少し前の書籍だが、ふっと手に取り購入した。ネットでこの人の記事を読んだ記憶があり、興味深かった。よくある自己啓発だが、やはりできる人の習慣は、当たり前のことを継続できること、特殊な考えで様式、行動ではない。しかし、ああそうだなこうだなと思うこともあり、参考になるものである。古典ではないので、何度も読み直すことはないかもしれないが、自己啓発本は置いておくと、あの部分にあんなことを書いていたなと思うこともしばしば。たまには読むといいですよ、この手の本は。

毎月、送られてくるFPジャーナルの特集で年金がテーマであった。WWP。就労延長、私的年金等、公的年金という頭文字をとって、年金の世界では言うようだ。完投型、すなわち就労をして、その引退後、公的年金と私的年金で賄っていくライフプランではなく、継投型、すなわち就労を長く伸ばす、つまり先発はなるべく長く投げて、次につなぐ。中継ぎは私的年金、繰り下げて抑えで公的年金のように力を蓄えることを推奨している。iDeCoも改正になりそうであるが、それだけ拠出できるお金があるのかというところには思うところがある。しかし、計画というのは考えて実践しないと果実は得ない。少しでもいいからその「投資」は必要である。

関税交渉もどうなるのだろうか、既存野党の勢力はどう動くか、自公政権の継続かなどなど、暑い夏がはじまる。「物価高対策」が争点というが果たしてそうだろうか。たとえば賃上げをしていこうというのはいいことであるが、急には難しいのであって、政治は長い目でみたマクロな視点と個別具体的なミクロな視点とが兼ね備えなければならない。どう考えても、消費減税とガソリン減税はすべきと思っている。前者は効果的な政策であると思うが、時期が遅いと言えば遅い。コロナの時にやるべきであった。給付金はあればうれしいが、財源があるのであれば、消費減税もできると思う。またガソリン減税は、租税の体系がくずれたまま。これもどうか。租税の原則がくずれている政策は他にもあるが、ガソリン減税は特に地方生活には必要な車にかかわるので、これは実現してほしいと思う。それにしても、今回は「政治」が動いてほしいと願う。全体的な政策は特に重視するが、上記、2点は野党と強調し、政策を煮詰めて導入すべきとは思っているが‥‥。

広島大学の図書館の利用の更新時期になる。慶應義塾大学と県立広島大学とここ、広島大学を利用させていただいているが、大学の図書館は時間を忘れていることができる。広島大学は古い蔵書がある、これが国立大学の強み。最近のものは極めて少ないというのが所感である。県立広島大学はWi-Fiが使えるが、今年から利用時間が短縮した。経費節減らしいが、これは学術機関としてはマイナスである。慶應義塾大学は上京時にしかいないが、満足のいく環境。蔵書もいつも増えているし、ここは没頭してしまう。そんなこんなで使える環境があるのは幸せなこと。お金をかけず満足度の高い施設が図書館と思える。

中小企業の方としゃべると、会計に関して「損益計算書」を重視しているように感じる。しかし、僕から言えば「貸借対照表」をいかに見るのかと考える。それは貸借対照表は、その会社の歴史が表れており、ここを見ると、よくわかる。この意味でもっと「貸借対照表」を重視したらと思うのだが、どうしても「損益計算書」のもうけに目が向く。それはわからなくもないが、一度、「貸借対照表」に力点を置いてみてほしい。殊更、最近よく思うこと。

久し振りに三原日本語学校へ。後期くらいから講師業も稼働することになると思うが、今年も元気よく入学をしている。だいぶ学校に慣れた感じで明るい表情があふれる。聞いていると、三原日本語学校の学生が地域に馴染み、連携もしているようだし、国際交流がうまくいっている模様。現場ではいろんな諸問題はあるかもしれないが、ここに日本語学校があるのは意義が深い。日本語教育も自分の武器になる技能であるが、日本語という語学はなかなか難しいものである。ひらがな、カタカナ、漢字・・・、文字もたくさん。日本語教育も新しいチャレンジ!楽しんでいこう。

2年に一度、AFPのFP継続単位を取得する。当初はFPに可能性を見出していたので、興味が強かったが、だいぶ薄れた。AFPから上級のCFPあるいはFP1級とステップアップすればいいのだが、どうも足踏みである。あれこれ将来設計は考えているが、あれもこれもの可能性を鑑みて、自分への最適解を探す。やはり年齢である。50歳も近くなると、終わりを見る。終わりを考えると、タイトルも本当に自分にいるものなのかは考える。新たなことを始めるのも前向きに生きる上で必要。しかし仕事という武器を考える際に、コレクターにもならないようにと思いつつ、戒めを考える。
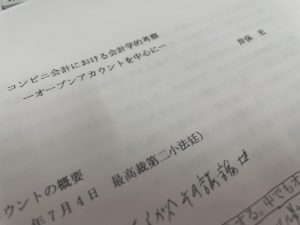
6月に出す予定の論文。少し見ていただいたら赤がまあまあ入る。進歩があるのかないのかと思うところ。ペーパーコメントと電話でご指導いただいたら、なるほどと思うことが山積。この数年、コンビニ会計をテーマに積み上げていく予定。直して提出して、次へ進もう。それにしても、博士号取得は過去のもの。やはり謙虚に向き合わなければね。農業ばかりではよくないと思い、近年、興味のあるコンビニ会計の領域へ踏み込む。学術界はどのように反応するかな・・・?
セミナー・講演会のご依頼は
こちらから受け付けております。
