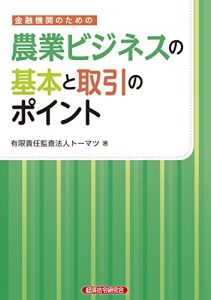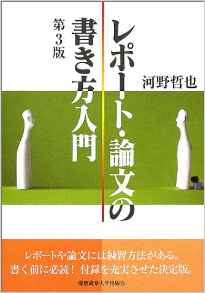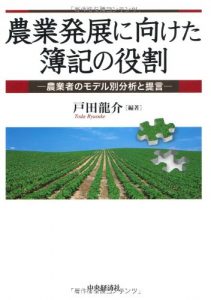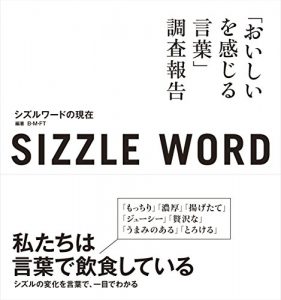学生達とのお勉強with再会
昨日はとあるFCの飲食店オーナ-のところにヒアリングをしてきました。県立広島大学の学生の皆さんと飲食業の会計実態の調査を先日よりやっています。とりわけ小規模な事業体ではどこまで会計の整理や管理、それをどう経営に活かしているのかといった点に着目しながら、様々な点を解明してきたいと思っています。管理帳表の正解はないため、どこまでやればいいのかということもあろうが、その帳表を使って、経営の判断材料にならないといけない。難しいなと思うと同時に、それぞれの業態や規模、いろいろ学ぶことが多いです。その後、オーナ-と二人になって、とある人と別の店で合流。1年以上ぶりの再会をし、旧交を深めたとさ。充実した1日でございました。
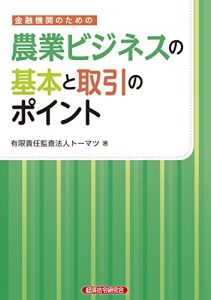
農業から広がる世界
農業を入り口にいろいろ考えてきて、行動もした。農業支援からはじまって、加工・飲食への広がりの中で、学術研究においても拡張せざるえなくなってきたというのがある。農業は生産の部分であるが、加工・飲食販売になると、やはり違う領域として、理論立てた計画が必要になる。あれこれ思いながら、農業を核とするならば、「食」、「医療」、「福祉」、「畜産」、「雇用」・・・・、様々な分野で連携や相互補完できる。農業ビジネスのあり方、そしてその考え方にもう一度、捉えなおして構築していくことが必要と考えている。ひとまず飲食業の連携の中で、僕なりの整理をしていきたいと最近思っている。
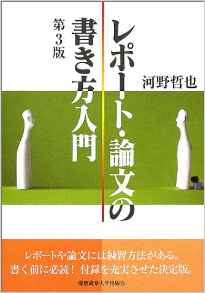
論文を書くとは何か
実家の本棚からかつて使っていた書籍の背表紙をみて、持って帰って再度読んでみた。こういったものを下敷きにやっていた気がするが、どうも自分流になっていたことがあるなと痛感。非常に参考になりました。この本には、過去の自分がラインマーカ-が引っ張っており、注意しながら進めていたのかと思う次第。どのように論文を書くのか、レポ-トをどうまとめるのか、入門的な手引書でわかりやすい。今、読んでももう一度フォームを整えようと再認識したものでした。歳をつれるにつれて、誰も教えてくれない。だから自分で学ぶしかないのだ。
 | 慶應義塾大学出版会 発売日 : 2002-12-13 |

大学生と共に
僕の現在の研究キ-ワ-ドは、農業・飲食業・クラウドファンディングの3つであり、基本は会計を基軸として学術的にまとめている。今回、学生と共にやっている調査は、飲食業の会計を焦点にヒアリングの中から帰納的にまとめていくことを主眼としている。過去の文献をさぐってみても、製造業や建設業などは多く管理会計研究はみられるが、飲食業は皆無に等しい。特に僕の感覚で言えば、成功の要因の一つに会計による経営把握がきちんとなされているところはぶれていない気がする。中小企業、とりわけ小規模なエリアで検討をしているが、どこまで科学的にやっているのか。味はおいしいが当たり前の前提あって、そこかた原価、販売管理費など管理をどうしていくのか。昨日の調査は目がうろこになる話であった。実務でも活かすのは当然として、研究面でも蓄積を重ねていきたいと考える次第。3つのキ-ワ-ドの最後の矢が放っていきたいと思う。
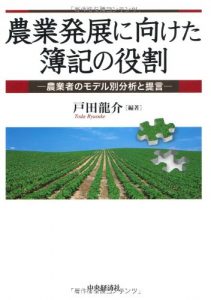
農業簿記に関する研究
2011年に農業簿記にかかわってから、自分の農業会計研究も「簿記」というものに着目して、章の一部になってきたような気がする。そもそも僕のくぐりとして、修士の際にまとめた農業会計の課題を学会で報告してみようということだったが、たまたま縁あって、農業簿記の部会にまで携わることになった。これも縁で学会賞まで共同であるが、いただき、画像の書籍もまで発刊。財務会計の世界にもヒアリングを重視した点が良かったように思う。そのときから日本簿記学会にも参加するようになって、今年の5月に久しぶりに報告したものを、今回、投稿する。簿記の領域が特に関心がつよいわけではないが、今回の整理したものは、簿記の領域で語るべきだろうと思っている。簿記にさかのぼることも必要なことである。査読が通るのか、わからないが、チャレンジあるのみ。学者はあらさがしが好きな人たちなので、またあれやこれやと出てくるんだろう。僕がそこにチュ-ニングすればいいのだが、僕にもプライドがあるので、譲れないところは譲らない。でも論文には意義がある。
 | 著者 : 中央経済社 発売日 : 2014-01-29 |

転職の例
社会人から大学教員に転身する人は多い気がする。どこかでキャリアチェンジをしたいと思う時期があるんだと思える。少し研究者の領域にかかわっているが、外から見ても一般の企業人より、拘束がなく、社会的地位も高いことから、大学への転職もわからないわけではない。学者の世界もいろいろあるが、僕もどこかで移るのかもしれないなと思うときがある。みんな一度くらいは転職は考えるときはあるのではないだろうか?
 | ディスカヴァー・トゥエンティワン 発売日 : 2013-09-09 |

久しぶりの大学講義
広島経済大学で、ゲストスピ-カ-の機会を得た。僕自身もはじめて行った大学である。今回は、鹿児島県立短期大学以来の「クラウド・ファンディング」のお話で、基本的なところから、日ごろ支援している事例を中心に展開した。大学生には社会経験がないことが大きいと思うが、難しいものなのかもしれないが、きっと大学の業界でもいろいろ出てくるだろう。近畿大学のハチミツの研究や、早稲田大学のラグビ-部のユニフォ-ムにしかり、小口資金の投資がこれからますます脚光を浴びる、そして身近なところで大学のキャンパスの中にも、地域のあれやこれやで出くわすことが多くなるだろう。不思議なことに、社会人向けに同一講義を頼まれたので、またお話できることになったので、今日の反省を基に再度肉付けして望みたい。広島経済大学の関係者の皆様、ありがとうございました!
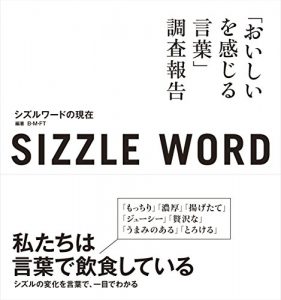
情報の「おいしさ」をキャッチする
人間はそれぞれに味覚があり、匂いや食感さまざまな部分で「おいしさ」を感じる。このおいしさは文化や地域にも異なるものもあるが、食に携わったものとして、認識しておかないといけない知識がある。それは言葉の「おいしさ」である。実はこのおいしさは情報で操作していくことも可能であり、「もちもち」や「ジュ-シ-」とか与えられた言葉によって、「おいしさ」をイメ-ジを沸かすことがある。つまり、言葉が持つ力をどう使いこなすという点は、与える側はきちんと理解しておく必要がある。この書籍。「おいしさ」の調査をいろいろ行っており、データがちりばめられているが、随分参考になる。商品開発やマーケティング、ブランディング等々、役立つと思える辞書として、ビジネスの場に置いておくのはいかがであろうか?

農業経営の導入編
投稿予定の論文に有益と思い、購入した書籍。前々からこの書籍は知っていたが、今回、財務管理という視点がどうしても必要なときに、他の方が引用文献の使用されていることから、改めて知った経緯である。農業経営の入門的に整理されており、たぶん教科書で使用されている学校もあるような本であった。農業の財務管理はなかなか見当たらず、先行的なものを手掛かりにする際にどうしても必要である。今回、再発見できた視点もあり、学術的導入では非常に読みやすくわかりやすいと思える。理論と実践を融合させていくのは、農業経営のみならず、必要な事柄だ。理論を軽視してはいけない。

今年で14回目
毎年、社会人大学院の有志とともに旅行へ行く。今年は仙台。ファイナンスの講義のときに、温泉に行こうということで、別府を皮切りに始まった。だから別研(他の意味もあるが、別府の始まりは『別』を入れる意味が強かった)。今年は別研メンバ-が死去したこともあり、みんなで献杯した。毎年、旅行に行って、1泊2日会話して、酒飲んで、風呂入ってやってるわけだから、濃い関係である。それだけにメンバ-の死去は我々にとっても、衝撃だった。さていつも写真撮らないから撮ろうと今回、とってみた。仙台城跡地である。大学院を修了して、10年。最初の頃は年に2度言っていたが、1回になったが、長く続いている。ほんと楽しみな行事である。生きている間に47都道府県廻ろうと意欲的である。1年1年の振り返りと共に、歳を重ねていく。素晴らしい仲間に恵まれている。来年は香川だ。