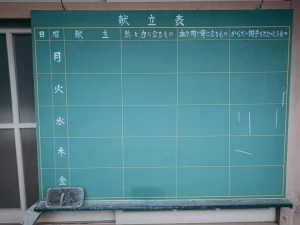上げるべきか下げるべきか
非常に興味深いニュースである。選挙における供託金を引き上げたらどうかという提案。現在、国政選挙で300万円の供託金がかかるが、それを10倍にした3000万円にして、候補者の乱立の見られる現象をなくし、選挙の質を高めようというもの。もし3000万円にしたらお金持ちしか出らればくなるので、これもどうかという意見もあるが、一考の余地はある。ただし国政選挙や都や府や県の知事選挙に限るとし、地方議会は定員割れもあるのだから、これは考えもの。3000万円までいかなくても、1000万円くらいはとも思う。僕が出た選挙は町村なので、供託金はなかった。あっても出ていただろうが、この頃は今のような混沌とした選挙ではなかった。時代も変わってきているし、公職選挙法は見直すべきであろう。そうそう、湯茶しか選挙事務所はダメである。珈琲はダメ。僕はきちんと守っていたが、だあだあになってはいないか?

大学は厳しいな・・・
先日、広島女学院大学の大学の経営承継が発表され、今回は比治山短期大学の閉校。4大は継続するようであるが、少子化の波は押し寄せてくる。これからこの流れは続くと思われる。基本金があるうちに、その決断をし、歴史を終えるのか。一部の学校は残ると思うが、やはり大学を作りすぎた。学士の価値を下げたと思うし、成長モデルの見誤りである。確かに一つ作れば、それに付随するビジネスも雇用も生まれるが、それは責任も伴う。大学経営陣は決断を迫られる時期に来ているが、将来はいかに?

自分では思わないこと
とかく自分には趣味がないということを嘆き、自分の中で変革を起こして生きようと。たまたま「ある人が僕にグルメですよね?」と言われたのだが、そこまで僕も思うこともなかった。確かに飯にはうるさい方だと思う。できればうまいものを食べたいし、その方が幸せ。会話だって弾むしとそんなことはつらつら思うことはある。しかし、自分がグルメで、それが趣味みたいなものとは思うこともなかった。ただしこれも違う土地に行って、老舗の料理店で食すというのも楽しみの一つだからこの手もありかなと思うところ。この前、呉に行ったときに見かけて今度行ってみようと思った南洲ラーメン。味が濃いのかなと思ったが、見た目と違いあっさり味。ふらっと食す楽しみ。これも心持一つだなと思ったお話。

住民の利用
写真は徳山駅であるが、これに隣接した形で図書館がある。その中にスターバックスも併設しており、おそらく蔦屋が指定管理者となっている模様。昨年、佐賀県の武雄市で見た図書館と同様な感じである。武雄市が駅とは隣接していないが、多くの人が利用していた。ここも見てみると、多くの利用がされている感じで、なんといっても利便性がよい。徳山に住んでいない人も寄っってみようと思うのではないか。図書館というのは、公共施設でも老若男女、利用するもので、人が集ういい場所である。情報拠点にもなるし、なんといっても、無料で施設を利用でき、本も借りれる。そう考えると、こうしたパターンで駅に隣接するなど利用しやすい場所を作るのはいいのではと思う。お金を使わなくても豊かな気持ちにさせてくれる空間を提供するのは大賛成。歩いてみて学びのある光景であった。

政治家への暴力
千葉県知事選挙にて、NHK党の立花党首がナタで暴力を振るわれている。安倍元総理や岸田元総理にも殺害へ及ぶこともあったが、やはり暴力はいけない。言論で理路整然とやるべきである。いろんな考えがあるから、それはそれ、やはり武力行使はやってはいかん。怖くて政治にも出られなくなる。思いを強くして、選挙にでるわけで元候補者としても心が痛い。日本が変わってきていることを目の当たりにしながら、もう少し有権者も考えるべき。主義主張はいろいろあるんだから、そこと暴力を同一視してはいけないと思う。

全国的に進むかもしれない
地域のことは地域で守るということが崩れるのか。崩れるというより地域で地域が守れないという証左。集落営農の子会社化という記事に、変わりゆく農業の形が進んでいることを真に受けた。経営継承できるところがどこになるのかというのもあるが、企業参入やあるいは海外の経営者が入り込んでくることは十分にあろう。今回、埼玉の農業法人さんが島根の農業法人を救済する形のようだが、すべてがハッピーエンドにはならず、経営も大変と思う。担い手だよね、やはり。そう思うが、この事例はこれから各所に出ると思う。注目事例であったので、記録までブログにとどめておきたい。
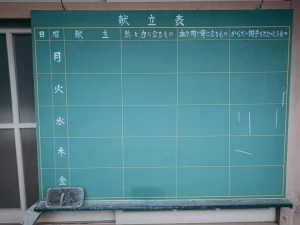
2026年度から?
早ければ2026年度から学校の給食無償化が実現するという。耳障りの言いことをいって、市町村の首長が選挙で公約したことが国で実現するのか。住んでいるところも学校の給食費無償化を公約したが、普通に支払をしている。まあだましあいのようなものだ。給食よりも実は諸費を公費で当てた方がいいように思う。これは学校のドリルや図工などの用具も含め、学校の授業で必要なもの。給食はアレルギーで食べられない子もいるので、強ちすべてがイエスとはいいがたい。弁当の人はどうするって?その一方で多くの生徒が食べるのだから食育、オーガニックというところも学ぶ機会はできる。それでも政策的に前進したのは評価したい。さてこれからどうなるのかと思いながら予算審議を見守りたい。

4年連続で人口の「転出超過」全国トップ
総務省が1月末に公表した2024年の人口移動報告で、47都道府県のうち「転出超過」が最も多かったのは広島県だった。その数は1万人を超え、4年連続で全国最多となった模様。住んでいて思うが、発展しているとは思えない。排他的な都市なので、外からの人は住みにくいだろう。若い人を考えてみる。政令指定市の割に大企業が少ないように思う。すなわち、就職の選択が少ない。次に交通アクセス。飛行機の利用は市内からかなり遠いので、移動の困難性。そしてテーマパークなどがないので、若い人の遊ぶ場所がないなど、あまりいい条件がない。カープはいるとしても、東京でも見れるとなると、住んでまでという話にはならないしと。まちづくりに真剣に広島県が取り組んできたと思えない。政治の失策が出ているように思う現実である。

田園回帰?
1月10日の日本農業新聞の1面に「移住過去最多24県」というタイトルの記事が上がった。移住調査で過去5年で24県が最多といい、田園回帰の流れが続き、若者世代が移住へ向かっているようだ。田舎暮らしでネックなのは仕事の確保である。田舎で育った人間は死ぬまでこの場所で過ごせないのを知っている。それは生活を確保する仕事がないからである。もちろん仕事を立派にしている人もいるが、都会と比べて機会が少ないのは事実と思う。そんな点で「関係人口」という概念が近年、よく聞かれるが、実際はどうなのか。週末田舎暮らしなどのライフスタイルなどうまくそれが出来る人はいいが、人にはそれぞれ状況がある。都会の一極集中はあまり芳しいとは思わないが、田舎にもリスクを伴う。お金は都会よりかからないかもしればいが、それだけ稼げないという事実はB面にあるなと思うところである。

もう受験もなくなるのか
僕は大学、大学院で今現在、4つの学位があって、学生の身分もたくさんさせてもらった。そして今は大学の教壇にも立っているが、現実的に「大学」って必要ある?と思いだした。偏差値にもよるところはあるが、Fランクと言われるところは高校の延長線上で、あまり進歩をしていると感じない。仮に私立大学で1年で学費が100万円だとすれば、4年で400万円。奨学金を借りるとすれば、将来の負債になる。その負債が人生の資産になればいいが、ほんとにそうだろうかと疑い深い。そもそも「学士」を持つ価値があまりにも下がってしまったのだ。「学士」を持つことで初任給は高く、より優位に社会人生活を送れるという方程式は今や崩壊している。そう考えると、大学に行く意味ある?と素朴な疑問である。社会人のリカレント教育が進むように、ほんとに必要であれば、そこから勉強をスタートさせた方がよりいいのではないか。今の大学にあまり魅力は感じないが、僕は研究もしているので、必要ではあるものの、自分の子どもが進学する頃にどういう見方になるだろうか。受験勉強はめんどくさい→安易な道の選択。そもそも大学行かなくていいよねってなるんだろうか。環境にもよるが・・・。