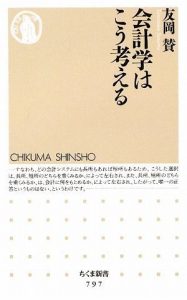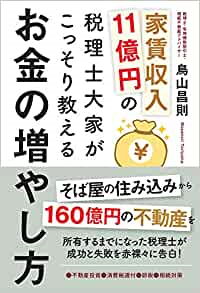発信の方法
最近、noteも始めた。ラジオを始めたのをきっかけにこちらでも書いていくことにした。ブログは、さまざまなこと、思うことなど、小記事形式で取り上げ、岸保 宏という横顔が覗けるような展開を記していきたい。一方で、noteはある程度まとめたもの、繋いでいけば書籍になるような感じで、コラム化したい。社会人大学院時代のことや農業、あるいは選挙挑戦のことを書いてもいい。そんなこんなでまとめていきたいと思っている。書いて公開し、一皮向けた自分と出会える、そんな好循環を期待しているが、果たしてどうか。ひとまずやってみよう。
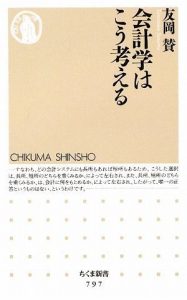
会計をほどく
来年からとあるところで、会計を教えることになった。初心者にどう会計を教えるのか。そして資格学校ではなく、大学で学ぶ意義。今から会計の初歩を学べるように、どう伝えれるかを模索している。昔、はやった会計の本など買いあさり少しずつ読んでいる。やはり自分でも改めて気づくこともあるし、これはいい機会になっている。農業会計ということでまだ活躍の場はないが、じっくりやっていけば花を開くときもあると思う。会計学も奥深いもの。僕にとって、令和という時代は大変革な時代になっているような気がする。

先行例を学ぶ
動画の活用はどうすればいいのか、コンサルタントのお話を聞いたり、自分で調べたりしている。この中でたまたま知り得たのが、予備校講師の森田哲也先生。英語の先生のようだが、YOUTUBEもうまく活用している。動画も何個か閲覧したが、なかなか面白いものである。さすがに受験生ではないので、受験生が得る情報とは違うが、英語にしかり、予備校業界の情報にしかり、いろんなものがUPされているので、一度見るといい。予備校業界も厳しいようだ。子供も減る、通信が発達している。その中で講師自身の付加価値をどう高めるか。科目毎に一人のスーパースターがいれば、いい時代だ。全国どこでもインターネットで有名講師の講義も聞ける。そう考えると、教育もボーダレスか。そうした背景の中、YOUTUBEに活路を見出していることは面白い取り組みだと思う。広告収入が講師料になる。予備校業界も情報公開の時代である。一度も会ったこともないが、注目している。動画の可能性はとかく感じる。どう取り入れるか、僕自身の課題の一つである。

最近の飲み方
コロナになってからあまり飲みに出なくなった。最近の楽しみ方の一つに、家のみのようにとあるスペースで集まって一杯やる。コロナ渦中とはいえ、やはり人とは集まってわいわいやる。わいわいやっていると、情報も集まるし、次の展開も開ける時がある。かつこういう飲み方だと、お金がほんとかからない。昨日は、焼肉などを中心に食事を楽しんだが、みんなで割り勘して、3300円。店で飲むと軽く倍の価格はするだろう。新しい生活様式もだいぶ慣れてきた。この時代、変化に対応できるものだけが残る。とにかく先入観は悪。そう思いながら生きていくこととしたい。

久しぶりの丸亀へ
長男の趣味にかこつけて、香川へ。100名城が香川県には2つ。高松城と丸亀城。ちなみに写真は丸亀城である。3年前に訪れたことがある。子供と回るのはまた別な思いもあり、いいものである。子供に学び、子供で再学習できる。こういうのは喜びである。子供にうどんが香川はうまいからと、綿谷にも寄った。時間がすいているときだったので、かなりラッキー。広島から日帰りしたが、十分な時間である。今回、時間配分もわかったので、また行くことにしよう。休日の使い方もどうするのか、これも楽しみである。

コンサルタントの付加価値
情報提供で農業経営アドバイザーの試験の案内をいただいた。政策金融公庫が認定する資格であるが、農業経営に携わる金融機関や税理士、診断士などには知られている。過去に6次産業化プランナーも歴任したことがあるが、農業関連での資格というと非常に少ない。技能・技術などは多いが、経営的なものは。今回、コロナの影響もあり、オンライン開催である。通常は東京に5日間べったり研修を受ける必要があり、地方の人にはチャンスである。そんなこともあり、今回は旅費交通費も考えれば、メリットは大きいような気がする。即日、400人の受講枠が埋まったようである。いろいろ学べるので、僕も少しは考えたが、資格マニアでもないので、これというもので勝負した方がいいと判断した。故に僕は受講・受験はしない。やはりこういうのも東京にいると、違う条件で考えられる。ただし、これからはオンラインなどどんどん変わっていくと思う。誰でもどこにいても、均等な機会を持つことが可能になるかもしれない。そうあってほしいと思うところだ。今回は締め切りだが、農業関連でコンサルタントを考えている人は、チャレンジするといいかもしれない。

新しい発想で!
最近、仕事も自分より若い人と仕事するようになってきた。比較的、僕は年上の人といることが多い。やはり物事を僕より知っているということもあるし、かわいがってもらったところもある。年上を軽視するわけではないが、少しずつ若い人とも触れ合いが増えてきて、何か違う刺激をもらう。年下にも違う時代で過ごしている分、僕の知らないこともたくさんあり、素直に聞ける。昔、「お前は年上との付き合いが多いから香典が大変だな」と年上の人に言われたことがあるが、それくらい年上とは付き合っていたものだ(今もそう)。たとえば、SNS一つとっても、若い人の使い方は違うし、ターゲット層ももちろん違う。こうしたことを肌で感じるのも大切なことであろうと思う。固定観念は悪である。近頃の若いもんはっていう人もいるが、僕は若い人にかなり引っ張られてる。引っ張られてついていくような感じだが、それもよし。自分に制限をせず、聖域をなくして向き合っていたいと思う。

本格的スタート
FM東広島で「農業のカルチベート」始まり、前回は自己紹介であったが、今回からゲストを呼んでスタートさせた。本日のテーマは農業と新規就農というテーマで、ウーベンアグリ代表の塩谷壮二さんをお迎えた。経験者の塩谷さん、異業種から初挑戦の鈴光さんのコラボは面白かった。事業を起こすには、お金がかかる。資金調達の苦労話をお二人で討論されていたのが印象的であり、塩谷さんも農業補助金とかもっと掘り下げた話もしたいと言ってくださった。楽しんで新しいことにチャレンジ。新たな幕開けにしたい。
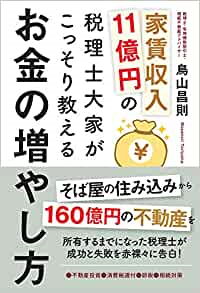
不動産賃貸業も事業です
まだ不動産価格は高い相場観はあるが、少しずつ値も崩れ始めている気がする。何分、売り物件がまだまだ少ないが、これから不動産を手放していく傾向はあるように思う。僕自身も不動産賃貸もしているが、この手の本は、ちょこちょこ読むようにしている。比較的多い投資をするにもかかわらず、不勉強な人は多い。僕も同じようなことが書かれていても、復習のつもりで読む。勉強する。不動産はインフレ時に強いなどメリットもあるが、当然にデメリットもある。しかし、何もやらなければ何もない。当然の帰結であるが、不動産を投資をし、お金の勉強をすることも大切な営みではないかと思う。税金もそうだし、投資効率もそうだし、登記なんかもそうだし・・・。一つの出来事で学ぶことは多い。この書籍は税理士さんが書かれた本であるが、節税なども書かれている。この類は多い部類の話であるが、いろいろ知識をインストールするといい。これから格安で不動産を得られることも出てくるように思う。有事に備えることだ。

転勤がてら
共同研究をご一緒した先生が松江へ転勤になったようなので、再会を兼ねて、松江へ。コロナの影響は、ド直球!週末だというのに閑散としており、静かな街並み。店主にも聞いてみると、ほんと少ないですねとのこと。やはり飲食店は依然厳しい状況は間違いない。閑話休題。三重に一緒した時以来だから、3,4年ぶりになるだろうか。お互いが博士号取得を追っかけていたが、どちらも博士号を取得し、新たな一歩を踏み出している。研究者として生きるのか、また「半研半X」なのかわからないが、僕もがっつりはできないが、徐々に稼働をさせていきたいと思う。論文は書かないと書けなくなる。吐き出せば、また身体に入る。たまに刺激を入れるべきだと感じる夜であった。