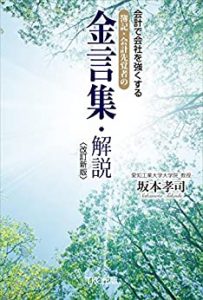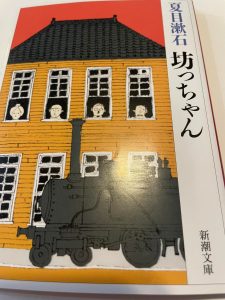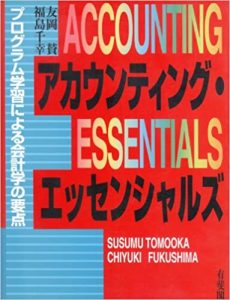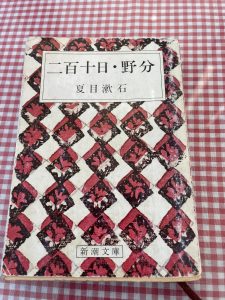いい先生を亡くす
共同研究もさせていただいたし、たくさんお世話になった成川先生の訃報が届いた。62歳だそうだ。あまりにも早い。10年前に共同研究をさせていただいて以来、いろいろご指導を賜った。著書も一緒に出せて頂いているし、そのときの論文も同じくした。学会でも再会の際にはいつも気に留めてくださり、ご配慮いただいた。よく酒も飲ませていただいた。仙台、国分町で二人で飲んだ時は楽しかったし、全国いろんなところでたくさん飲んだな。学問上でも非常に読みやすい論文で、どうすればこうした論文が書けるのか指導を受けたこともある。目標だった。もう会えないと思うと寂しい限りだ。どうやっても葬儀に参列できない。その点、成川先生、お許しをいただきたい。安らかにお休みください。ありがとうございました。
 | 著者 : 中央経済社 発売日 : 2014-01-29 |

ぱっとはしないが・・・
月末までに論文を出そうと思い、ようやく書いたが、内容は今一つ。しかし、まあそれなりにというところだろうか。学者のはしくれとしても、やはり論文は書かないとと思うし、学生にレポートを課すなど,権力を持った人間からすれば、自分を律しないと教壇には立つ資格がない。だから何とか年に1本は思うところ。今年度はできれば、もう1本出したかった。どうにもこうにも忙しくて、手がつけれず、意地で1本やったが、どうもしっくりはきていない。実力不足である。それでも何とかと思うのは、自分がどうあるべきかを考えることが必要だからである。次に何とかいいものを残せるように頑張ろうと思う、それにしても悔しさの残る論文だ。

そろそろ書き上げないと・・・
確定申告の仕事が忙しくて、ほんと何も出来なかった。フルでエンジンをかけて、論文を書かないといけない。論文として残していかないといけないものもたくさんあるのも承知。いつまで経っても、タスクは減らずである。この数年、論文としては農業の税務に焦点を当てる。ただし、問題意識が違うのかなと思いつつ、また思案の連続である。苦しいことを逃げずにやるしかないんだけど、忙しいので、つい逃げたくなる。それでもやるしかない。この本はコンパクトにまとまっているので、実務家にはいいのではないかと思う。
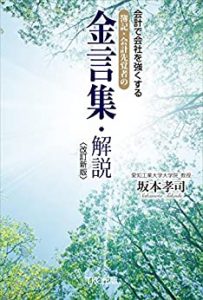
教養のある雑談
今年の会計学入門の際に何個か学生に話をする際に使わさせていただいた。なかなか面白いもので、会計の教養ある言葉を集め、解説している。これはお勧めである。会計というと固い話になるので、ちょっと導入してみたのを思い出した。来年はどうするかなと思いついたこと。今日は短くこの辺で。

絶対的な基礎的部分
最近、知った本だが、これはいいなと思った。高校生までに知っておきたい2000ワードのようだが、クイズのように問題があり、以下で解説している。高校国語を分析して選んだようだが、結構ハイレベルなものもカバーしているし、これは将来的に子供にもそれぞれ買い与えようと思う。おすすめ。やはり語彙が不足していると、論理といってもそのレベルの基礎的前提がないので、話が進まない。最低限、基礎的な部分は絶対的に必要と思う。子供がもう少し大きくなって、一緒に学べるときが来るといいなと思うのだが、果たしてどうなるだろうか。その時まで少しずつ学んでみたいと思う。
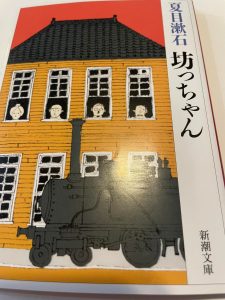
坊ちゃんから学ぶ
漱石を少しずつ読み直している。今回は坊ちゃん。言わずと知れた作品だが、1週間から10日で書かれたと言われる小説であるが、素直に坊ちゃんの成長小説として読めばいいと思うが、それでもなお深く考えるのは、清の存在、死というものから人生を考えるというか、その人が死んでも、受け継がれるもの(人)の中で生きるんだという命題を与えられているような気がする。そして、教壇に立つようになってから、教師の正義感とか思うこともある。漱石はやはり面白い。もう一度読み直そうと思っているが、なかなかうまく時間がコントロールできない。できるなら、少しサバティカルのような休息が欲しいなと思う今日この頃。

今の職業だと・・・
昔も書いたことあるが、僕の仕事で言えば、完全に逃げ遅れた。あれよあれよと逃げれなくなって、結局、立ち止まっているような感じである。会計事務所の仕事だと、確定申告時期は縛られる感じがある。期限が迫っているので、どうしても仕事をしないといけない。量も多いので、仕方ないが、それにしてもこの時期が毎年、こういう状況というのも機会損失と思えることもある。昔、さっぽろ雪まつりに行ったことあるが、たまたま連休にもなって、もう二度といけないかもしれないと思い切って行ってみた経験がある。もしもう少し有給でも取れてゆっくりできるなら、もっと違うこともできるのかなと思ったりもする。仕事があるだけありがたいのだが、人間はないものねだりである。「もし、たら、れば」ということは多い。それにしても、毎年忙しくなっているのは気のせいだろうか。

リスタート2022
久しぶりに論文を起こしている。この2,3年は少し論文を残していこうと思っているが、僕の研究キーワードのひとつ、集落営農法人について何本かまとめようと思っている。平成13、14年ごろに積極的な集落営農の法人化を政策的に進めたが、それから20年が経過した今、集落営農法人はどうなってるのか、学術的にも実務的にも興味深い。持続的な地域保全の道はどこにあるのか、深堀しながら考えてみたいと思う。ヒアリングもたまには必要だと思うが、理論にしっかりよせて脱稿したいと思っているが・・・。
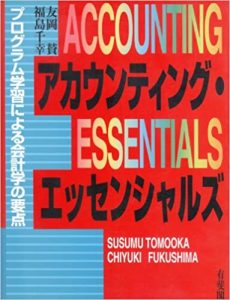
何とか終えました
中国学園大学で1年を対象に、会計学入門という講座を担当した。15回と長丁場であったが、何とか終えることができた。終わってみて、もう少しこんな話したかった、こうすればよかったということはたくさんあるが、最低限、伝えるべき内容は言い尽くせたと思う。それにしても、どのレベルに合わして話せばいいのか、どうすればもっとよりわかりやすく伝えられるのかなど、真剣に悩んだ。一生懸命、駆け抜けた15回であったが、学生たちにはどう映っているのだろうか。最後に難しかったかどうか尋ねてみると、一様に難しかったという。大学は難しいことをやりに行くところだから、簡単ではない。自分たちも悩み、しっかり学習し、一皮むけていくしかない。また来年も岡山に呼んでいただいたので、バージョンアップして戻ってきたいと思う。
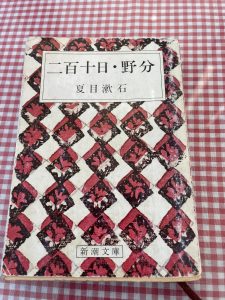
白井道也は文学者である。
白井道也は文学者であるという有名な書き出しで始まる「野分」。漱石が新聞小説家としてデビューする前の最後の作品。漱石から何か生きるヒントというか、この混沌とした今を打破する糸口を探せないかと思っている。野分を読み直して、教壇に立つようになった今、感じるものが多い。教師はお金儲けでやる職業でないし、お金儲けをするには商人であるということも書かれているが、当時、学者というものが崇高な存在であることも見て取れ、今のサラリーマン化した学者像とは全く違う。言葉に魂があるというか、勉強になることが多い。野分は漱石の中でもマイナー小説だと思うが、一読してほしいなと思う小説の一つ。