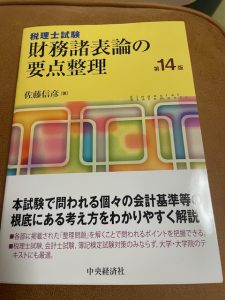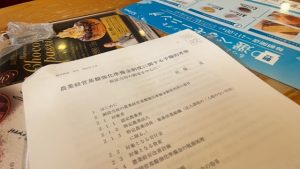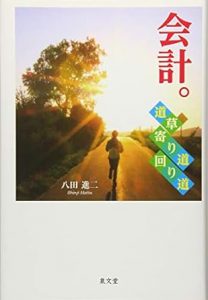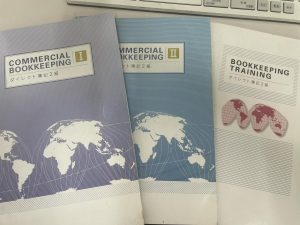ほんと「謙虚」なのか
一応、専門はと聞かれると、「農業会計学」と答えているが、その農業会計学は、農業経済学の一端から派生しており、その一部として考えていい。僕の立場からすれは、社会科学で育ってきたと思うが、最後は自然科学の農学部出になるわけで、ほんとどっちつかずで生きているのは間違いない。そのどっちつかずの僕が先日読んだ「農業経済学の意義」で違和感を感じざるを得ない。謙虚という言葉が果たして適切なのか。中身を読むと意味はわかる。「本質的な構図をシンプルな概念で提示するのが農業経済学の役割」、「能動的に日本の農業を内外に発信することが重要である」ということは理解できる。果たしてそれが「謙虚」なのか。ぱっと言葉が浮かんではこないが、「謙虚」ではない。そんな所感を得た記事であった。
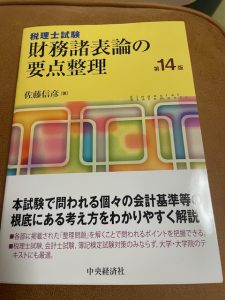
書籍謹呈
税理士試験向けであるが、第14版の財務諸表論の要点整理を頂いた。試験向けと銘打ってあるが、中身は充実、コンパクトにまとまっていた。学び直しにちょうどいい。この書籍、税理士試験とか銘打たない方が多くの人に目に触れるかもしれない。しかし、14版までいくということは評価を得ているのに評することでもないか。それにしてももっぱら会計系は読むことが少なくなった気がする。農系が多いわけで、純粋な会計学者ではないということの証左か・・・。頂かないとめくることもなかったかもしれない書籍だが、これはほんといい内容であった。そもそも会計学でいいなと思うものが少ない。だからなおさら貴重。
 | 中央経済グループパブリッシング 発売日 : 2023-09-27 |
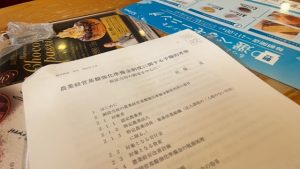
忙しさに輪をかけて
論文の校正が届いた。いつも忙しい時期に来るので、時間がほんと取れない。正確さも欠ける性格なのに、輪をかけて加速する。いかんぞいかんぞと思いつつも。研究者もどきとしては、やはりいい悪いは別にして、論文を出していくことが必要に思う。僕にも意地があり、何が何でもというところで壁を越えようと頑張っている。自分自身との闘いである。今年度は2本。そのうちの1本が手元に。あれこれあるが、ここは踏ん張り時である。それにしても、パソコンばかり見ているので、目が疲れている。身体より目。寝つきも悪いし、脳も疲れているのかもしれない。さすがに歳を感じる。校正も締め切りまでには何とかやりきらなければと思う今日の朝。

実務大敵!
仕事の工数がかかりすぎる。こんなにやらないといけないことが増えているし、これ、できる?っていう理論と実務の乖離が甚だしい。これなら素直に12パーセントにするとか、複数税率を辞めて、一律10パーセントに消費税をするなど、租税の原則である簡素へ立ち戻ってほしい。計算様式が変わる、書式が変わる、非常に手間であり、ほんとインボイスは廃止してほしい。政治資金規正は緩いが、国民には厳しい。これ、考え物。複数税率を取りやめ、インボイスを辞める。ほんとにやった方がいいと思う方策。

ここは踏ん張り時
年末年始にかけて、論文を2本提出する予定である。手直し等を含め、大詰めである。なにせ年末だから、何かと忙しいし、電話、メール、来客等・・・・。重なるときは重なるものである。しかし、どうしても論文は出さないといけない。研究者の端くれとしては、論文を出してなんぼである。いい悪いというのもあるが、一区切りして、前に進む。その繰り返しである。今回、だいぶ煮詰まってきた感じもあり、今後、まとまってくるのではないかという期待感もある。それだけに一歩一歩進むしかないと思うし、ここは踏ん張り時だと思う。頑張った自分しか助けてくれない!
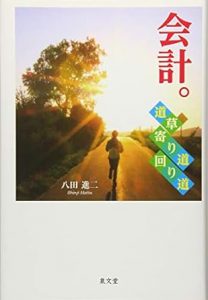
僕からしたら斬新
会計学を大学で教えている身からすれば、「会計」とあると反応する。パブロフの犬ではないが、ブックオフによった際に見つけた本である。基本的には買う前は目次程度でも中身を見て買うが、この本は価格も見なければ、中身も見ずに購入した。何故か、「会計。」というタイトルはストレートで斬新、とてもいい。副題はあるが、それは付随したもので何か期待されるものであった。もう一つは、研究者をやっていると八田先生のお名前は聞いたことはあるもので、素直に学んでみようと。そんな話である。中身である。会計大学院のことを含め、会計プロフェッションの育成について真摯に意見を述べられている。会計軽視にある状況に看過できない、あるいは危機感を抱いていることが十分に伝わる内容であった。会計プロフェッションの育成までいかなくても、会計軽視というか会計の重要性といったところを教えられれば(学生に伝われば)と思うが、果たしてどうだろうか。コラムでいいので何か、こういうお考えをさらに公開して読みたいと思うものだった。
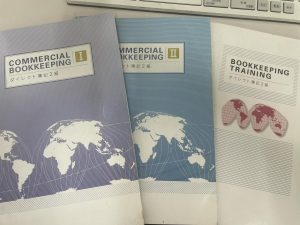
バック トゥ ザ ベーシック
たまに見返す簿記の教科書。一昔前、Z会が資格事業をやっていた頃に使ったものである。Z会は特に独学なので、教材、よくまとまってると思う。この教材は初学者が一気に簿記2級まで駆け上がるように作成されてるので、3級と2級の境目という点はあるが、僕には教える上でも参考になる。検定の範囲が変わっているようだから、試験の観点ではもう使えないかもしれないけど、今風に改訂すれば、とてもいい教科書だと思う。Z会さん、復活させてほしい講座ですよ。

会計の重要性を考えよう!
会計を教えている、会計の仕事をしている。そういうバックグラウンドはあるが、どうも経営者の会計軽視の姿勢が目につく。日常が忙しい、営業が忙しいというが、稲盛さんではないが、「会計がわからんで、経営ができるか」というのはないだろうか。コロナが明け、補助金なども支援がなくなっている今、コロナで融資も増え、銀行も回収に入っており、企業の姿勢や態度を見ているように思う。「まあ、何とかなるだろう」、「何とかしてくれるだろう」と安易に思う。お花畑思考である。もう黄色信号から赤信号になっている。企業側も真剣に会計を見て、経営再建する。それでももう銀行もダメと判断すれば、倒産へ向かわせるだろう。売上UP、販路開拓の素敵なお話を聞くのもいいことだが、足元の点検、会計をきちんと構築する。企業の地味な構造改革こそ、未来につながるのではないかと思うのだが・・・。結局、会計を重要と考えていないのが起因であろう。

意味があるのか
インボイスは離農を促進する作用になる。農業の所得向上からも遠くなる。インボイスは事業者の負担も大きく、本制度はほんとにいただけない。複数税率を辞めて、10パーセント統一、帳簿保存方式で事務負担も減り、税収も上がる。簡素な税制を望む。委託にすれば、収入の確保はさらに少なくなるわけで、本末転倒。産業育成が経済を回す。インボイス制度は廃止すべきと思う。別のやり方もないのだろうか。

初参戦!
学会嫌いの僕が意を決して出陣、島根大学へ。幽霊会員であるが、やっとオンラインから脱却したようだから、向学のために参加した。税法の学会なので、作法がまた違う。法学は判例である。違う頭を使いながら、こうかなああかなと聞いたものだが、何分、素人の域を越していない。そう思いながら聞いたものだ。それにしても国公立大学は予算の関係もあるのだろうが、暑い!。クーラーが効いていない。ほんと汗をダラダラ流して、参加しないといけないというのもどうかと思う。私大がやはりいいなと思うものだ。やはり学会は苦手な場である。新しい人と会うのは、とかく疲れるもの。ほとんどしゃべらず、会場を後にする。意外と人見知りなのである。