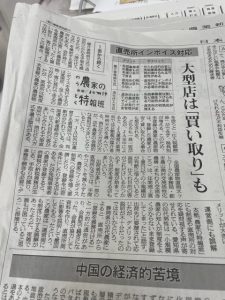採点の時期
この時期になると、採点をする必要がある。僕自身が大学は論文を書きに行くところだという信念があるので、レポートを課している。しかし、レポートの精度が低く、1年生ということを加味しても厳しいなというのが印象。来年からその「信念」は捨てないといけないかもしれない。自分の与えられたコマではそこまで教えるのは、時間的にも無理。今回、この本を見つけて頼んでみた。最初は失敗してもいいから、作法がいるよと思うのだが・・・。あとあと自分が困ることになるので、僕は行っているのだが、伝わっていない気もする。常勤の先生にそこら辺はお任せして、コマに徹しようかと3年目で思い始めた。
 | 慶應義塾大学出版会 発売日 : 2014-10-21 |

考える力
共通テストの振り替えで岡山に講義へ。だいたい正月明けまでにレポートを学生に提出させる。1年生のレポートだから、出来不出来もあるが、まず「出来ない自分と向き合う」こと。孤独のレッスンと言えば、格好がいいかもしれないが、そんな格闘を望み、そこから出た言葉に期待している。しかしながら、語彙力、教養の低下を年々感じる。つまり論理だの、思考だのと言う前に、その素養がないため、ファンダメンタルなところが欠けているから、前へ進まない。詰め込み教育がということも言われるが、ドリル的に漢字や単語、計算などの訓練が必要ではないかと思う。今どきの大学生を見ると、自分の子供が受けている教育、親から子への教育など考えること、満載なのである。大学は論文を書きに行くところだと僕は思っているので、レポートを通じて、思うこともたくさんある。さて、採点という仕事が僕には待っているな~。

論ずる内容
農業会計学を一応、専門としているが、より深く考えてみると、僕の中での「農業会計学」というのは結論がついたのではないかと思う。改めて何を論ずることが今のところ、ないのではないか。つまり、関心や興味ということもあるが、ひとまず博士論文で仕上げたことが今なお、僕にとっての「農業会計学」ということでおさまりがつく。完成度が高いというほどではないが、確かにこうだと自分でも思えるので、それでいいのではないか。そのときに次のステージにうつることになるだろうし、劇的に状況がかわらない限り、今現在は現在完了ということになろうか。やり切ったという感じでもないが、やり切ったと言えるのかもしれないなと今更ながら思った日々雑感。

一度、会ってみたいな~
たまたまネットで見つけた国語教師の吉田裕子さん。会ってみたいなと思う人である。サイトを見ると、カルチャーセンターや予備校や自分自身の教室、執筆などやられているようである。中でもvoicyを使って、10分間教養講座をやっているようであるが、なんといっても声が素晴らしい。聞きやすい。これは大きな強みである。ほんとに国語、日本語といったものが好きなんだなとも伝わるし、面白いなと思い、たまに拝聴することにした。たくさんのことをやっているようだが、ビジネスセンスもあるような気もする。会える機会がどこかでないものだろうかと思うところ。僕より歳も下のようだ。まだまだおじさんも負けてられない。

岡山も長くなったものだ
岡山で講義をさせてもらえるようになって、3年目である。講師室でも事務室でも図書館でも話す人は増えた。見知らぬ時間講師ではなく、皆さんよくしてくれる。せっかく岡山に行く機会があるんだから、もう少しいろいろ楽しんでみようと思っている。今回は早めに岡山に入ったので、名物のえびめしやへ。なかなか独特の味。岡山はほんと縁がなかった。岡山は新幹線でも通過するし、そう用事もない。だから岡山のことは隣の県でもよく知らない。講義の前後で時間が何等かとれるわけだから、ぶらりとするのもいいかもなと思い始めた日々雑感。

繰り延べた現実
長いコロナでの自粛。アフターコロナと言われる今、いろいろしわ寄せがきているように思う。農業は保護産業であるが、それでも破綻はする。保護産業と言えども、民間事業であり、営利を求める以上、当然であるが、厳しい現実と言わざる得ない。負債総額も約35億円、売上がコロナ前で16億でも債務超過は間違いない。相当無理な経営をしてきたのだろう。やはり農業は設備投資がかかり、それに見合うリターンがあるように思えない。しかしながら、衣食住の人間の根幹を支える農業をどのようにとらまえるのか。そんなことを考えながら、農業法人の記事を読んだ。

農地を巡る制度史
やはり歴史を知るというところからは逃げられない。それだけの地脈があるもので、こういうものを読めばわかることは多い。なぜならば。今あることが突飛に出てくる話ではなく、その延長線上にあるからである。どうもこの前から、「農業者」、「農地」という観点が気になって仕方がない。いろいろ読むが、当座、これが一番詳しそうだ。部分的に読んだものなので、流れに沿って少し読んで見ようと。ただ太い本なので、読破には時間を要するが・・・。ただ研究者が読む本と言える。
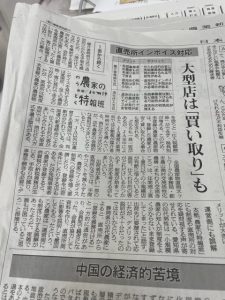
インボイスは廃止すべきだ
どう考えてもインボイスは混乱しかない。他の徴税方法を考えるべき。今日の農業新聞であるが、施工日が近づくにつれ、現実をたたきつけられる。個人的な見解であるが、インボイスの悪評は高いのは、おそらく政府もわかっているだろう。だから支持率が下がるのを恐れ、政府CMもしない。普通だと、「インボイスの登録はまだですか?」と啓蒙のCMが嫌というほど流れるはずだ。それもない。しれっとスタートするのだろう。この記事では、直売所のインボイス対応について特集しているが、消化仕入方式であると直売所の経営は成り立たなくなるのは容易に予想できる、しかし、これをしないと直売所には農作物は集まらないだろう。今回、思うのは、インボイスの制度設計をするにあたり、幅広い検討がされたのかどうかである。あまりにも小規模事業は、社会からの追放が気がしてならない。やりすぎである。消費税の複数税率を辞めて、10パーセントに統一することの方が皆さんにも理解がしやすいと思われる。ただ再考税収は近年続く中、税徴収がどんどん厳しくなっていくのは危惧でしかない。

時系列な俯瞰
農業者をどうとらまえるか、農地を巡る制度、ここが農業を考察するにあたり、重要な要素である。改めて読んで見たが、大変勉強になった。特に今、平成5年の農政の局面のところに着目して研究しているので、やはり流れを把握すると、農政の動きから見えてくるものもある。そこは論文に落としたいと思う。それにしても、農地法たるものはどこかで学ぶ機会がないだろうかと思うものだ。できれば、農学系より法学系で。そこは何故かといえば、法律を読む所作の点検と新たな知見を得るような気がしてならないからである。意外に自分が学ぼうとするものは、出くわさないというのもある。だから「研究」なんだろうかと思いつつ・・・・。


意味があるのか
インボイスは離農を促進する作用になる。農業の所得向上からも遠くなる。インボイスは事業者の負担も大きく、本制度はほんとにいただけない。複数税率を辞めて、10パーセント統一、帳簿保存方式で事務負担も減り、税収も上がる。簡素な税制を望む。委託にすれば、収入の確保はさらに少なくなるわけで、本末転倒。産業育成が経済を回す。インボイス制度は廃止すべきと思う。別のやり方もないのだろうか。