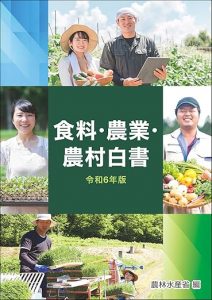現実である
少子高齢化の進行、農村での人材不足の深刻化において、新規就農者がここ5年で1万人以上減っている。2023年では43,460人であり、49歳以下で言うと、15,890人という。新規就農と言えども50歳をこえてから就農するようである。農の雇用事業として、農業法人などえ働く新規就農者は研修生39.5%が離農という結果っでもある。離農理由は現実と理想のギャップ、給与や勤務体系、体力的な問題等々、いわゆる「ミスマッチ」になろうか。農業従事者が減る。地域の衰退、疲弊はさらに進むだろうが、重点的な支援を求める。しかし、抜本策は僕もよくわからない。食料がないことは国力の停滞でもある。やはり手厚い支援は少なくとも必要ではないかと思う次第。

個人経営にも社会保険?
農林水産省が個人経営体の従業員の社会保険、労働保険の義務化の検討をするという。農業基本法の改正で、「(農業現場での)雇用の確保に資する労働環境の整備」を求めていることもあり、幅広い分野での社会保険の適用をということらしいが、季節のばらつき。費用、事務負担など、農業経営者には過酷な話にも思う。労働法が労働者保護にあることは理解できるが、経営者は守られることもない。確かに「こうなればいいよね」って話は、社会にもたくさんちりばめられているが、すべてに「YES」にもならない。正しいことがすべて正しいというのが社会ではない。今回の社会保険、義務化は踏みとどまってほしい。担い手の衰退、離農の促進要素にもなるのではないかと思うものである。ただ流れ的には「義務化」になるのではと思うが、机族の望むように。

もっと「コメ」を作りましょう
今回の自民党の総裁選で、コメ政策が争点に浮上という記事を見た。増産に舵を切るということ。水田活用の直接支払交付金の財政負担が米需要減に伴って増えていることや、増産分の消費の確保はできるのかなど問題は山積である。海外へのコメ輸出に活路を見出そうとすると考えであろうが、実現はいかに。しかしながら、担い手を確保し、食料自給率を上げていかなければ。この国は埋没することになる。どこにお金をかけて農業生産を落としている国があるのかという石破先生の意見はもっともである。さきほど申し上げた輸出→実現の方程式が本当に成り立つのかである。もしそれがなければ、コメの増産分の消費の確保がないわけであるから、米価の下落は避けられない。農業所得は減り、離農というシナリオも否定できない。今回の総裁選、農業政策にも注目したいと思う。

中長期的な視点で
農業新聞を読んでいると、農業高校の教員の成り手がいないという記事を見かけた。産業教育手当で、大半が支給金額(給与の10パーセント)を下回っているという。農業高校で言えば、準備もさることながら、飼育や実習、農場管理など時間外労働の賦課も多い。財政上も問題としているが、教員の確保はさらに難しくなってこよう。採用試験でも半数以上が辞退しているというのだから、労働環境は決していいとは言えないのだろう。人を育てるのに、やはり時間を要する。お金だけの問題ではないかもしれないが、それに似合う報酬というのは必要ではないか。待遇悪化は続くような気がする。ほんとに人がいなくなってから、本機になるのだろうか。問題は未然に防ぐ。再考すべきではないだろうかと思う、農業高校の教員問題。
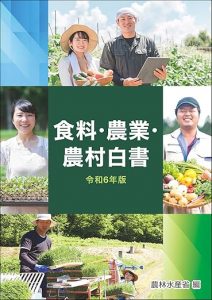
毎年のこと
例年になるが、農業白書は目を通す。だいたい7月に発刊されて、送ってもらうようにするが、何故だか8月に届く。本屋で買えば、持って帰るのに重いので、送ってもらうが、今年は農業基本法の改正もあって、農政にとっては重要と思われる。どの分野でも興味関心がある分野は目を通した方がいい。流れがわかる。ネット時代になっているが、やはり書籍で目を通すのは大切であるし、表紙をみていると手に取ることもある。白書を読むときは夏であるが、夏ということは下半期に入っているんだから、もう今年も終わりになってきていることなのかと感慨深い。

中山間地域の農業から
昔、広島県の農産物のブランドの仕事をしていた時に、抜群の農産物で登場された世羅の恵様へ毎年、とうもろこしを分けて頂く。他にお裾分けしても、抜群の評判の一品。ブランドの審査の時も、審査員も評価はかなり高かった。そんなこんなで7,8年はゆうに経過しているだろうが、時期を見計らって、参るわけだが、先駆的に動いている。やはり近年は天候不順の影響が大きいようだ。これはここの農家さんだけではないが、深刻な問題である。どうも広島県は農業支援という点でかなり弱いと思うのだが、当分ご無沙汰もしているので、もろもろ聞いてみたいものだと思うところ。円安の影響もすごい。未来の農業はどこに・・・。そんな諸々を思いながら1年に一度の訪問をした記録である。

農業問題
これは先日の記事であるが、本日の日本農業新聞でも農業経営体90万割という記事が出た。国内の農業生産をいかに維持するのかが課題となっているが、若手の農業参入には所得の低さもあるし、創業資金の確保などなかなか進まない。離農、新規就農・・・・・担い手の問題は大きいなと思うところ。集落営農を中心に研究をすすめている身としては、地域維持には必要な要素であるが、問題の繰延をしているだけで抜本的な解決はしていない。どうすればいいのか、おそらく農業の場合、事業を軌道に乗せるには7年はかかると思う。まずもって創業資金がかかりすぎる。ハウス一棟建てると、今や5000万円近い。軌道にのせるまでの支援をどうするのかをもう一度構成すべきと思う。食は人間生活の根幹を担う。食料自給率が40パーセントなら、60%は食べられないということ。輸入に頼るだけではいけないのでは?2割減と言えば、10000人から8000人ということ。100万人なら80万人である。そういう事実を受け止めるべきであろう。

中山間地域へ
少し遠めの農業法人へお仕事。まあいろいろ話していると、あれこれ出てくるもので、いいコミュケーションが取れたのかなと思う時間でした。内容は言えないけれど、たまに農業の現場に行き、学びを得ることをしていかないといけないなと思いながら、どうしても農業の仕事になると、ちょっと遠めの位置にあることから時間がとか言い訳となることもある。まあそうは言わず、動かないと改めて思ったところ。農業の仕事もまだまだやりますよ。写真は道中でランチ。

農業経営者の時間配分
日本農業新聞で経営のツボというコーナーがあり、たまにUPされる。今日、たまたま掲載された記事であるが、農業生産と農業経営のバランスたるものを整理されているが、結論を言えば、こうだ。「これからの農業経営者に大切なことは、農業生産の力を落とさずに農業経営の時間を確保し、自らの農業経営力を高めていく」ということになる。儲かる農業経営の実現の本質が農業生産にあるということを言われているが、6次産業化など加工に走るのではなく、根幹がやはり生産事業をどう構成して経営していくかということになる。どうも生産事業を軽んじるような傾向に踏み入りがちであるが、やはり基礎基本に立ち戻り、農業経営をしていくことに他ならない気がする。農業経営という観点への意識は強めることは必要であるが、自己点検は基礎基本からである。

なんでもかんでも
野菜が高いね、ほんと。今日の日本農業新聞では、キャベツの小売価格が過去5年で最高価格という見出し。天候などもあるにせよ、食は生活の根幹、値上がり傾向がなんでもかんでも続いているので、 ほんと生活が厳しくなっている。飽食時代と位置付ければ、もう一日2食ということもありうるかもしれない。それだけ日本は貧しい国となってしまった。最近の記事では、新興国転落というワードも見たが、まさしくそう、正面から事実を受け止めなければならないだろう。野菜の高騰をみると、ほんと手軽には食が食べられなくなった。さらに離農も増えるだろうと思うし、悪循環。暗いニュースが多いなあと思うが、それでも生きていかなければいけない。なんとかならないだろうかと思いつつも・・・。